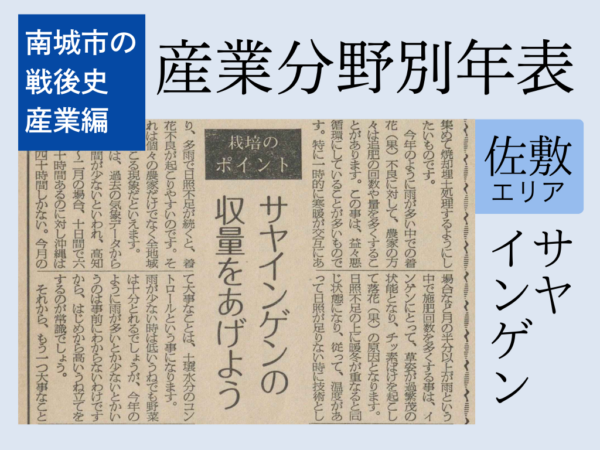
産業分野別年表 サヤインゲン(佐敷エリア)

産業分野別年表 キュウリ(佐敷エリア)
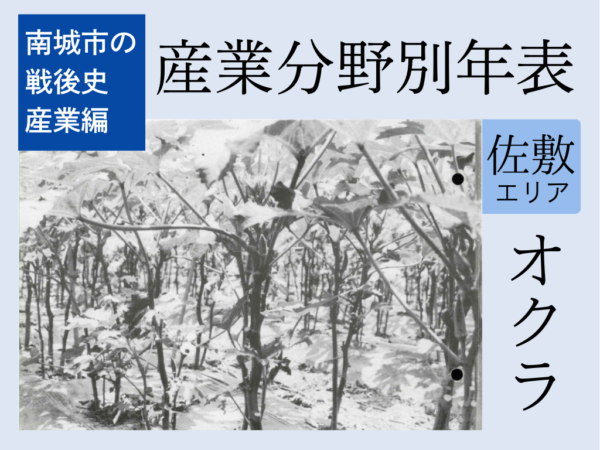
本稿は、湧上洋さんのオーラルヒストリー (2)「戦争体験記」の続編です。本稿では、まず、湧上さんがミントゥンの会のボランティア活動の一環で、小学校で戦争体験を語った時に配布した資料を一部掲載します。次に、その資料の内容やそれに派生する様々なことについて湧上さんが筆者に語ったことを、インタビュウ形式で記します。そして、最後に、用語解説を記します。
ここでは、湧上さんが2017年7月7日船越小学校で、平和学習の講演を行った時に配布した資料の一部を掲載します。同資料は、湧上さん自身が執筆したもので、「私の戦争体験」と題されています。本稿では、その中の第4章「4.遠足で見た戦跡」だけを掲載します。終戦から1年以上が経過してもなお、戦争の爪痕が生々しく残っていたことを、湧上さんは伝えています。
なお、筆者は、読みやすさを考慮し、元号を西暦に変えるなど、若干の校正を行いました。
4.遠足で見た戦跡
1945年10月、富名腰(現船越)は解放され知念市船越区が誕生。翌月11月26日には船越初等学校(現在の船越小学校)が誕生した。
翌年の1946年、船越初等学校の6年生になった私は学校の遠足(戦跡巡り)に参加した。鉄血勤皇隊隊員(師範学校生徒)だった男性の先生と、ひめゆり学徒隊隊員だった女性の先生が引率した。
摩文仁へ行く途中、道に半分埋まった靴底を取り出すと、人骨が出てきてびっくりした。また、摩文仁の丘に上る険しい山道近くで、片手に水筒を抱いたまま倒れている軍服姿の兵隊の遺体を発見した。そのように、戦後1年が過ぎても未収集の遺体が存在していた。
摩文仁の丘の一番高い山には突き出た岩山があり、その側には第32軍司令官・牛島満と参謀長・長勇の墓標(現在の「黎明の塔」)が建てられていた。当時それは木柱であった。また、その周囲には砲弾で砕かれた岩石が散らばり、戦争の痕が生々しく残っていた。その近くに第32軍司令部壕の洞窟があったが、その壕の入口には、艦砲射撃を受けたために白く剥き出した砲弾の痕や、火炎放射器で焼かれた痕跡が残っていた。 鉄血勤皇隊隊員だった先生の話では、軍隊と共に首里から摩文仁に撤退した鉄血勤皇隊は、摩文仁の丘頂上の第32軍司令部壕を中心に、南側の崖下の洞窟や岩陰に陣を構えたという。そこから200メートル先にある、海岸近くの井戸(金井戸)から飲料水を運搬したり、食糧を運搬したりすることは、鉄血勤皇隊の仕事であった。海上のアメリカ軍艦からは絶えず艦砲弾が飛んで来ていたので、険しい山道で水を運搬する隊員仲間が目の前で多数怪我したり亡くなったりした。戦跡を案内してくれた先生も両足に怪我を負った。
また、井戸には、多くの日本兵と避難民が水を求めてやって来た。アメリカ軍の海からの砲撃で多くの犠牲者が出た。井戸の周りは死体であふれ、その光景は地獄絵図のようであったという。
摩文仁からひめゆりの塔に向かう道の両側には、至る所に砲弾で削られた穴(艦砲の穴)が数多く見られた。それは、そこがものすごい激戦地であったことを示していた。
ひめゆりの塔周辺の原野には、砲弾で切断されたり火炎放射器で焼かれたりした松などの枯れた立木が見られた。また、そこには砲弾で崩された岩石が飛び散っていた。
ひめゆり学徒隊のいた第三外科壕(擂り鉢形洞窟)には、米須集落近くに収容されていた真和志村民(村長は金城和信氏)によって、壕周辺の原野や畑に野ざらしにされていた遺体が納めされていた。その壕の側には木柱の墓標と「ひめゆりの塔」と刻まれた石碑が建てられていた。後になって、納骨所がひめゆりの塔の敷地内に設けられ、それらの遺体はそこに納骨されたという。
ひめゆり学徒隊であった先生の話では、第三外科壕の深く広がった壕内には、ひめゆり学徒の先生・生徒45人と、軍医・看護婦・衛生兵および一般住民あわせて100人ほどが避難していた。米軍のガス弾攻撃で80人余りが壕の中で亡くなったという。モンペの切れ端を濡らしてそれを鼻に当てて助かった人もいたという。
遠足では、摩文仁・米須一帯に、戦後一年経過したにも拘らず、暴風のように砲弾が降って来た「鉄の暴風」の生々しい痕(砲弾で崩れた痕)などを目にする事が出来た。また引率の二人の先生から自らの体験した話を現場で聞く事が出来た。そのことで、摩文仁・米須一帯が大きな激戦地であったこと、多くの人(住民)がアメリカ軍の集中砲火で犠牲になったことを理解できた。
ここでは、前章の「遠足で見た戦跡」で記された内容を含め、戦前戦後の様々なことについて、湧上さんが筆者に語った内容を、インタビュウ形式で紹介します。
■引率した先生■
――引率なさった先生の1人は、ひめゆり学徒隊の方ですが、名前を覚えていますか。
はい。仲栄真澄枝先生です。現姓は謝花です。
――『ひめゆり平和祈念資料館 HIMEYURI PEACE MUSEUM official guide book』によると、当時17歳で師範予科3年生。糸数分室勤務だった方ですね[ひめゆり平和祈念資料館資料委員会執筆・監修2004:121]。
そうです。仲栄真澄枝先生の戦争体験の手記は、玉城村が発刊した『糸数アブチラガマ(糸数壕)』でみることができます。先生は、生徒1人ひとりに寄り添って親身になって指導する情愛の深い方でした。
――鉄血勤皇隊隊員だった先生の名前も覚えていますか。
はい。糸数正行先生です。現姓名は、川崎正剛です。糸数先生は、先頭に立って積極的に行動する正義感の強い先生でした。後に、大学を出て弁護士として活躍し、県の選挙管理委員長を務めた方です。
■戦前教育■
――前回のオーラルヒストリー (2)「戦争体験記」の取材後に、さらに質問が出て来たので、今回、あらためて、戦前や終戦直後についていろいろとお話をうかがいます。まず、教育勅語についてお聞きします。湧上さんが執筆なさった「戦争体験記」には、教育勅語は「意味も分からないままに一字一句丸暗記させられた」と書かれていますが、どの程度厳しい指導を受けたのでしょうか? 覚えられない子供もいたと思うのですが。
なかなか覚えられない子供もいましたが、全員、暗唱させられました。教員は、全員が暗唱できるようになるまで、徹底的に生徒を指導しました。字も難しいし、意味も分からないのに、我々は、覚えさせられました。今でさえ完全に意味がわかるわけではありません。あれを子供たちに覚えさせても、何の効果もなかったのではないでしょうか。
――そのような無意味な暗記をさせられても、生徒はみな、反抗的にならずに、軍国少年でいたのですか。
はい。皆、軍国少年でした。当時の教育は、疑問を感じさせないほど、徹底した軍国主義教育だったのです。
――とはいえ、なかには、ひねくれた子供や、冷めた目で大人を見る子供がいてもよさそうですが、実際にはどうでしたか。数は少なくとも、そういう子供はいたと思うのですが。
そのような子供はいませんでした。そのような子供が出てくる空気はまったくありませんでした。子供たちは皆、当然のように軍国主義教育を受け入れていました。
――しかし、家庭内では本音で、当時の国家体制に批判的なことを言うことはあったのではないでしょうか。
ありませんでした。大人から子供まで、当時の空気に染まっていました。
――当時は、天皇中心の時代でしたね。湧上さんの体験記や平和学習のレジュメを見てもそれがよくわかります。奉安殿の例をひとつみても、戦後では考えられないことです。
ええ。当時、我々は、玉城国民学校の校門から入ると、まず、右側の高台の上にある奉安殿に向かって最敬礼をしました。それなしに、自分の教室へ行くことはありませんでした。
――奉安殿の中に人間がいるわけでもないのに、それに向かって最敬礼をするのはおかしい、と思う人はいなかったのですか。
いなかったです。皆、真面目に最敬礼していました。
――天皇は天照大神の子孫であるということを学校教育で教わったと思いますが、皆、そのような科学的にありえないことを信じていたのですか。
子供たちはみな信じていました。当時の大人がどうであったかはわかりませんが。
――戦後、科学的でないことを信じ込まされていたことに気付き、怒りを感じるようになった、ということはありますか。
そのような記憶はありません。私個人もそうですが、周囲の人でも、そういう話をしている人を見たことはありません。
――「天皇の赤子」という言葉がありますが、遠く離れた本土の天皇の赤子と言われても、信じ難いのではなかったですか。
大人であればそのように判断できたかもしれませんが、当時小学5年生だったので、素直に思い込んでいました。なにせ、その考え方は徹底して教えられましたから。
――敵は鬼というイメージを持っていましたか。
鬼畜米英という言葉の通り、英米人は鬼みたいな人かなと思っていました。
――当時湧上さんは10歳でしたが、そのくらいの年齢が、一番洗脳されやすいのかもしれませんね。小学校の高学年の子供は、大人の話す内容(ある程度複雑な内容)を理解する能力を身につけていますが、その一方で、精神は未熟で、素直です。
たしかにそう思います。
――「戦陣訓」についてお聞きします。「生きて虜囚の辱めを受けず」「死して罪禍の汚名を残すことなかれ」などの言葉は、沖縄戦関係の本を読んでいると、よく出てきます。軍人も民間人も皆、そのような考えを持っていたのでしょうか。
民間人に関して言うと、みんながみんな、そうではなかったと思います。兵役から戻ってきた人と接することがあった民間人は、戦陣訓の教えを知っていてもおかしくはありませんが、そうでない民間人は、戦陣訓の影響を受けていたとは思えません。少なくとも、私は当時戦陣訓の教えを叩きこまれた記憶はありません。
――家庭で「戦陣訓」の考えを教わるということもなかったですか。
なかったです。父親は、教員でしたが、軍国主義的な教育を家庭内でおこなったことはありません。
――「捕虜になると女の人は辱めを受ける、子供は又裂きにされる、男は殺される」と信じていて米軍に投降できなかった、というような話は、書物で頻繁にでてきますが、この点について、湧上さんはどのように記憶なさっていますか。
私自身の記憶はありませんが、私が船越で聞き取り調査を行っていた時、それと同じような話を聞きました。捕虜になることは危険であると信じていた日本兵が、そのことを民間人に言っていたようです。たとえば、米軍上陸後の4月末頃、親しくしていた兵から「自分の壕に隠れていなさい。逃げてはいけない。敵に見つかったら危険だ」と言われた地元民がいます。
■方言の使用■
――ウチナーグチで話すとスパイ扱いされるので、ウチナーグチの使用は強く咎められていたという話を本でよくみかけますが、湧上さんも、同様の経験をしたでしょうか。
このへん(富名腰)では、そのような抑圧はなかったです。ウチナーグチを話して叱られたという経験はありません。武部隊の日本兵は紳士的で、ひじょうに親切でした。かれらが、「ウチナーグチを話すな」と言ったことはありません。武部隊の兵とは異なり石部隊の兵は、高圧的で恐れられていましたが、かれらとの接点自体が多くあったわけではないので、石部隊の兵が「ウチナーグチを話すな」と言っていたかどうかは、わかりません。少なくとも、私個人はそのような経験はありません。当時、石部隊の兵と接触のあったのは、主に炊事班の女性でしたが、炊事班だった女性からそれについての話を聞いたこともありません。
――学校では、ウチナーグチ厳禁だったのでは? 戦前について語られる時、学校での方言札の話がよく出てきますが、私には、方言札の記憶が曖昧です。少し強調されすぎているように思います。勿論、学校ではウチナーグチは禁じられていました。でも、学校から帰った後は、子どもは外でも、家庭でも、ウチナーグチで話していました。それを叱るような大人はいなかったです。たまたま外で日本兵と遭遇した時は、標準語を話したが、それはウチナーグチを話すと怒られるという恐れからではなく、ただたんにウチナーグチだとコミュニケーションが成立しないからでした。
■武部隊と石部隊■
――武部隊は、富名腰(現船越)の住民との関係は良好だったとのことですが、戦後、復帰直前に、武部隊の牛山中隊のメンバーが、14,15名ほどで船越を訪問したということが、それを物語っていますね。
武部隊の牛山中隊は富名腰区に駐屯し、民家に間借りして生活していました。兵たちはメーヌモー(集落前方の山)で陣地壕を掘っていましたが、壕掘りの作業を終えたら、集落東側のウッカー(大川)で水浴びをしていました。夜も、ウッカーの松林の丘で夕涼みをして過ごすことがありました。彼らにとっては、ウッカーとその周辺は特に懐かしい場所でありました。しかし、彼らが復帰直前にそこに行った時には、草が生い茂っていて、ウッカーの水量も減少し、様変わりしていました。それを見たかれらはガッカリしました。
――石部隊は、逆に高圧的で、住民から良く思われていなかったとのことですが、具体的に、どのように高圧的だったのですか。
たとえば、石部隊は、強制的に、野菜などを供出させました。戦後になって聞いた話ですが、当時住民の食糧にも余裕がなかったので、区長は軍と住民との板挟みにあって苦労したとのことです。また、石部隊は、区長を通して、陣地構築に住民を動員しましたが、その時の態度も高圧的だったそうです。区長は軍に協力しなければなりませんでした。軍は恐ろしい存在だったので、軍の要求を断ることはできませんでした。
――武部隊と違っていたのはなぜでしょうか。
比較的戦争の少ない満州から沖縄に来た武部隊に対し、石部隊(第62師団)は沖縄に来る前に中国にいて、激しい戦闘を行っていたといいます。そういうことで石部隊の兵たちは沖縄の人に対し、粗野な態度を取っていたのではないかと、戦後、文献を調べている時に思いました。
――なるほど、アジア歴史資料センターのグロッサリーによると、石部隊は、次のように解説されています。「1943年6月、独立混成第4旅団、及び独立混成第6旅団主力を基幹として、山西省太原、及び山東省で編成。第一軍の隷下に入り、山西省東南地区の防衛に任じた。その後、数々の作戦に参加。1944年3月には第12軍の隷下となり、河南省攻略作戦に従事した。7月、転戦のため開封に集結、支那総軍の隷下となり、さらに編成整理を命じられ大本営直轄となった。8月、上海に前進し呉淞より乗船し那覇港に上陸」
中国での戦闘体験というのは、やはり横暴になった原因の1つかもしれませんね。
――ただし、武部隊も、中国での戦闘経験を有していました。同グロッサリーで、武部隊は次のように記されています。「第一次上海事変、第二次上海事変、南京攻略戦、徐州会戦、武漢作戦に参加した歴戦の精鋭部隊。1940年に衛戍地の金沢から満洲国牡丹江市に移駐し、第3軍隷下で牡丹江省を警備。しかし、沖縄方面の防備強化のため、1944年7月に首里市へと移駐。第32軍の隷下で、南部の島尻郡の防衛を任された」
ですので、中国での戦闘経験の有る無しで、武部隊と石部隊の違いを説明することは難しいと思います。ただ、石部隊(第62師団)は、有名な三光作戦(※「3.語彙解説」参照)に参加しているので、この作戦についてよく知ることで、石部隊の特徴が少し見えてくるかもしれません。
なるほど。
――三光作戦は、林博史教授の著作『沖縄戦が問うもの』では、こう書かれています。「三光作戦のような治安粛清作戦は山西省などでおこなわれたが、その山西省などで編成されて沖縄に送り込まれてきたのが、第62師団だった。山西省での日本軍による性暴力被害者たちが1990年代に日本政府を相手取って訴訟を起こしたが、その残虐行為にかかわっていた少なくない将兵が沖縄に来ていた」[林2010:39]。
私も文献で同様の記述を目にしたことがあります。
――なお、中国華北で三光作戦に参加し沖縄戦でも戦った近藤一さんは、戦後「兵士達の沖縄戦を語り伝える会」を結成し、中国と沖縄の体験について伝える活動をなさっています。近藤さんは、石部隊の独立混成第4旅団第13大隊第2中隊に所属し、嘉数高地の激戦で生き延びた兵士です。『母と子でみる44 ガマに刻まれた沖縄戦』という本で、次のように、彼の中国での体験が記されています。「1940年に徴兵されると、ただちに中国山西省遼県へ送られ(中略)初年度教育を受けた。立木に縛りつけた中国人捕虜2人を、70人ほどの初年兵が銃剣で突いた。刺突訓練である」[上羽修1999:63]、「山西省は八路軍の強いところだった。その解放区に対する掃討作戦に明け暮れた。いわゆる『三光作戦』である。討伐で部落に入ると、まず女性を探し輪姦した。そのあと性器に瓶や木片を押し込む。女性は悶死した。古年兵はよくもこんなひどいことをするものだと思ったが、しばらくすると初年兵も同じことをしていた。また、10人ほどの捕虜を縦1列にピッタリくっつけて並ばせ、背後から小銃で撃ったこともある。一発で何人が撃ち抜けるかテストしたのだ。捕虜は殺すものだった」[上羽修1999:63]。
そういう経験をしたら、感覚がおかしくなってくるのかもしれませんね。
――近藤さんは、日本兵が中国で蛮行に走った原因の1つが皇民化教育であると、語っています。同書では、次のように記されています。「子ども時分からの差別教育ですよ。天皇は神で日本は天皇をいただく神州の国。したがって日本民族は世界一優秀な民族である。それにひきかえ支那人や朝鮮人は劣等民族。支那のチャンコロは人間ではなく豚以下だから殺してもかまわない。そう思って育ったのです」[上羽修1999:63]、「共産党支配地域の中国人は殺せば殺すほど天皇のためになる、何をやってもかまわないと思っていました。だから口に出せないような蛮行をいっぱいやりました」[上羽修1999:65]
たしかに教育の力は大きいです。
――近藤さんは、沖縄に駐屯し始めた頃、沖縄人に対する差別的な感情を抱いたそうです。その原因は、沖縄は、中国と似ていて、日本本土とは違った点があるということです。同書では、その点について、こう書かれています。「沖縄は日本本土とどこか違っていた。まず言葉はわからないし主食がサツマイモである。寺も神社もほとんどない。それに人糞を食わせる豚の飼い方が中国山西省と同じだった。『琉球の人たちは中国から渡ってきた民族で日本人とは違う、と思ったんです。そういうところから小学生時分以来の差別意識がでてきて……』」[上羽修1999:65]
文化的な違いが、差別の感情を生んだのですね。たしかに中国の文化と沖縄の文化には多くの共通点があります。
――まとめて言うと、山西省での三光作戦の体験、少年時代からの皇民化教育、沖縄と中国の文化の共通点などが、石部隊の粗野な態度を生み出したということになります。
しかし、当時のことを大括りに話すのには違和感を覚えます。その本の読者は、石部隊の全員が沖縄で素行の悪い兵だったような印象を受けるかもしれませんが、それは事実とは異なると思います。石部隊の皆が、沖縄人に対して横暴だったということはないと思います。また、高圧的であったとしても、個人によって程度の差はあったと思われます。
――近藤さん自身も、沖縄でずっと、差別意識を抱いていたわけではないようです。時間の経過とともに、意識は変わっていったとのことです。同書でこう記されています。「宿泊していた民家のおやじさんと親しくなったり、陣地構築などで住民と一緒に汗を流すうち、沖縄の人も同じ日本人だという一体感が培われてきたという」[上羽修1999:65]。
共に生活をしていると、理解し合えるようになりますし、情も移ってきます。やがて、家族のようになってきます。
■平和学習■
――ミントゥンの会の活動で、長い間、小学生に沖縄戦の体験をお話しになってこられましたが、小学生から難しい質問がくることはありますか。
たまにあります。例えば、「なぜ、戦争をすることになったのですか」という質問です。小学生が理解できるように答えるのは難しいです。それに、戦争に至る道筋はたくさんあるので、専門的な知識がなければ答えにくいです。ですので、簡単に「日本は資源の乏しい国だから、資源を求めて海外へ出た」といった言い方しかできません。
――資源を求めて大陸を目指したのは事実ですね。
しかし、海を渡ったのは日本だけではありませんでした。イギリスは香港、ポルトガルはマカオへ進出しています。日本だけが悪かったのではありません。当時、中国が弱ってきたので、列強は中国を目指しました。やがて、アメリカを中心とした国々による経済制裁により、日本が追い込まれ、アメリカと戦うことになった、ということではないでしょうか。しかし、沖縄にとっては、戦争(アジア・太平洋戦争)でいいことは何もなかったです。
――日米対決の原因について、湧上さんの見解に近いことを述べている学者がいます。マーク・セルドン(コーネル大学東アジア研究所教授・東アジア史)は、読売新聞のインタビュウでこう話しています。「19世紀末から20世紀序盤にかけ、米日が、急速に台頭しつつある、新興植民帝国だったことを忘れてはならない。日本は、日清戦争で台湾を領有し、やがて朝鮮を我が物にする。米国は、スペインとの戦争でフィリピンを植民地化し、東アジア進出の足場を築く。拡張主義路線を走っていた日米両国は、1930年代の満州事変、国際連盟脱退以降、衝突が避けられない状況になったと見ている」[読売新聞戦争責任検証委員会2006:196]。湧上さんの考えに近いと思います。
そのような分析をしている学者がいるのですね。そういうことは言えると思います。
――マーク・セルドンは、さらに、「日本はどんな方策をとるべきだったのか」という問いに対して、こう答えています。「恐らくは中国から手を引くことがその解答だったと思うが、日本は逆に、自分たちより強い相手(米国)に戦争を仕掛けるという極端な冒険主義に出た。(中略)日本の冒険主義により、アジアの国々、米国、日本自身が大きな代償を払うことになる」[読売新聞戦争責任検証委員会2006:196]。今は、逆に、日本は、アメリカから中国との対決をそそのかされているように見えます。これにのっかり、中国と対立することも冒険主義と言えるのではないでしょうか? ウェブ・メディア「情報・知識&オピニオンimidas」の連載コラムで、猿田佐世氏は、2023年2月20日付「安保三文書改定で日本が平和になるならこんな楽なことはない ~台湾有事で米軍基地を自由に使わせるな」というタイトルの論稿で、こう述べています。「もし台湾有事が起きたとしても、日台で軍事同盟を結んでいるわけではないので、日本が台湾を防衛する『義務』というのは存在しない」と。つまり、冒険主義を捨てて、中立の立場をとるという方針を固めることで、中国との戦争のリスクを回避することができるというわけです。一方で、有事の際に、アメリカが台湾を支援する形で介入したら、日本はアメリカに協力すべきであるという考えもあります。これらのことを考えた時に、日本はどのように外交を進めるべきだと思いますか。
もし台湾有事が起きた場合、中立の立場をとるべきかアメリカに協力すべきか、日本はどのように外交を進めるべきか、私には、直ちに結論を出すことは出来ません。いずれにしても、中国との戦争のリスクは回避すべきであると考えます。
――日本は、ミッドウェー海戦で空母を4隻失い、その後も負けこみました。1944年7月にはマリアナ諸島が米軍の手に落ち、それらの島からB29がノンストップで日本本土に飛来して航空爆撃ができるようになりました。1944年10月にはレイテ沖海戦で連合艦隊の主力を失いました。その時点で敗戦の色は濃厚になりました。形勢が悪くなっていく中で、もっと早く、アメリカと講和交渉を始めるべきだったかもしれません。沖縄に関して言えば、多くの沖縄人がいたマリアナ諸島が陥落したことは大きなショックだったに違いなく、その時点から、沖縄では、和平を求める空気も少しずつ生まれてきたのではないか、と私は想像するのですが、実際はどうだったでしょうか。当時、そのような空気はあったでしょうか。そろそろ和平交渉に入るべきであるとか、このままでは負けるとか、劣勢を立て直す術はないのではないかとかいった冷静な意見が聞かれることはありましたでしょうか。
私はそういう空気を感じたことはありません。和平交渉をすべきというような意見は聞いたこともありません。教養のある人や、情報に通じていた人の中には、そういう人がいたかもしれませんが、私の周囲にはそういう人はいませんでした。また、かりに、そう思っていても誰もそう言えなかったのではないでしょうか。当時は、日本は絶対に勝つということしか言えなかったです。それに、ほぼ全員が、本当に日本が勝つと信じていたと、私は思います。
■戦後■
――沖縄戦は生きのびた人の心に大きな傷を作ったと、私は想像します。戦後、宗教により心を癒すようになった人もいると聞いたことがあります。例えば、船越で、キリスト教に帰依することにより、心を癒すようになった人はいますか。
私の知る限り、戦後、戦争で得た心の傷を癒すために、キリスト教に寄りかかるようになったというような人は、船越ではいないです。玉城冨里に教会がありますが、そこのキリスト教徒は別の理由でクリスチャンになったと、思います。
――残された世代は何をしなければならないと考えますか。
戦争というものはよくないことだということを学んでもらいたいです。まずはよく知ることが大事です。私は、学校で子供たちに話す時、「戦争をするな」とか「平和を守ろう」とかいう言い方はあまりしていません。体験した戦争の恐ろしさ、悲惨さだけに限定して話します。当時起きたことを話すことにより、子供たちがそのことを理解し、興味を持ち、自ら学ぶようになってくれることを願っています。戦争というものがいかにむごたらしいことかを理解してもらいたいです。
これまで述べてきた内容を深く理解するために、以下、重要な用語や出来事について解説します。
【ひめゆり学徒隊】
ひめゆり学徒隊(戦後の通称)は、沖縄陸軍病院に動員された沖縄師範学校女子部と県立第一高等女学校の教職員と生徒のこと。3月23日に動員命令が出された[吉浜忍ほか2019:125]。
沖縄師範学校女子部では、157名が動員され、81名が犠牲になった。一方、沖縄県立第一高等女学校では、65名が動員され、42名が犠牲になった。ひめゆり学徒隊の配属場所は、沖縄陸軍病院(本部・第一・第二・第三外科)壕群、一日橋分室、識名分室、糸数分室、第三十二軍津嘉山経理部壕。勤務内容は次の通りであった。壕掘り、伝令、水汲み、飯上げ、食糧調達、死体埋葬、排泄物の処理、薬品運搬、患者担送、患者の食事の世話、患者の排泄物の世話、注射、包帯交換、手術補助(照明用ローソク持ち、切断する手足を押さえる仕事、切断手足の処理)[ひめゆり平和祈念資料館資料委員会2004:38]。
【ひめゆりの塔】
湧上さんが平和学習用に作成した資料には、湧上さんが遠足でひめゆりの塔に行った時の様子が次のように記されています。「ひめゆりの塔周辺の原野には、砲弾で切断されたり火炎放射器で焼かれたりした松などの枯れた立木が見られた。また、そこには砲弾で崩された岩石が飛び散っていた」これは、戦後間もない頃の光景です。1948年、大城信子氏(元なごらん学徒)は、文教学校を卒業して帰郷する際、トラックで南部戦線を回り、「ひめゆりの塔」で下車しましたが、その時の様子を次のように述べています。「約6畳の広さの壕の底一面に、お骨がこんもりと山積みにされ、頭蓋骨は岩陰にずらっと安置されていた。余りの残忍な光景に遣り場のない憤りと悔しさが込み上げ、玉代勢秀文先生や東風平恵位先生、師範へ進学なさった先輩方のお顔を思い出し、涙が止まらなかった」[青春を語る会2006:248-249]。
ひめゆり平和祈念資料館の敷地内に、第三外科(ひめゆりの塔の壕)がありますが、1945年6月19日、この壕内に米軍が投下したガス弾のために、35名の生徒が最期をとげました[仲宗根2015(1982):362]。生徒の中で生き残ったのはわずかに山城信子氏と大城好子氏、守下ルリ子氏、金城素子氏、座波千代子氏の5名で、職員は全員死亡しました[仲宗根2015(1982):366]。なお、生徒以外では、職員5名、看護婦と、炊事婦29名、兵隊、民間人6名などが犠牲になりました。総計約百名の者が第三外科洞窟で悲惨な最期をとげました[仲宗根2015(1982):417]。守下ルリ子氏の手記は、その時の様子を次のように伝えています。6月18日の学徒隊の解散命令が出された後、第三外科壕から出ることになりました。6月19日、壕からの脱出の機をうかがっていると、敵兵の声が聞こえてきました[仲宗根2015(1982):377]。壕の入口で「コノゴウニジュウミンハイマセンカ。ムダナテイコウハヤメテ、デテキナサイ。デテコナイトバクダンヲナゲコミマス」という呼びかけがありました[仲宗根2015(1982):377-378]。しかし、誰も動こうとしなかったので、ガス弾が投下されることになりました[仲宗根2015(1982):378]。
金城素子氏の手記には、黄燐弾が2回、最後にガス弾が1回うち込まれたと記されています。金城氏は、「『天皇陛下万歳!』と叫ぶ声や『海ゆかば』をうたっている声、先生や母を呼ぶ声、そして級友の名を呼びつづけている声を聞きながら倒れていった」[仲宗根2015(1982):390]と述べています。座波千代子氏の手記には、彼女が意識を取り戻してから見た光景について次のように書かれています。「あたりを見渡すと、先生も、お友達も、看護婦も兵隊もおりかさなってふくれあがって死んでいた。誰の顔だか全然見わけがつかなかった。銀バエが何万匹とたかり、悪臭が鼻をつく」[仲宗根2015(1982):405]。ちなみに、座波氏は、ガス弾投下前の第三外科壕内の様子について、次のように記しています。「この壕に来てからは、収容の患者はごくわずかで、仕事もなく、百余名の者が目白おしにくっつき合って身動きも出来ずかたい岩の上にすわってじっとしているだけだった。尻のいたさや、悪臭にたえ、毎日毎日すわりつづけている単調な時間は、砲弾をくぐるよりももっとつらい難行であった」[仲宗根2015(1982):399-400]。戦後、1946年の春、金城和信氏夫妻が中心となり、摩文仁に集まっていた真和志村民は、ひめゆりの塔を建立しました。そして、4月7日、近在のひめゆりの同窓生と村民が集まって除幕式と第1回の慰霊祭を挙行しました[仲宗根2015(1982):417]。1948年6月、沖縄基督青年会は、民政府工務部の援助を得て、納骨堂を建立しました。そして、1948年6月22日、第2回の慰霊祭が行われました[仲宗根2015(1982):421]。
1985年6月に催された「ひめゆりの塔」の慰霊祭において、女子看護隊の生存者を中心に設立された「ひめゆり同窓会」の代表は、式典の中で次のような弔辞を述べました。「私たちは、みなさんの死が殉国の美談にすり替えられることを恐れます」[山崎2005:185]。
【沖縄師範学校】
1880年に設立された会話伝習所が起源。名称を1881年に沖縄県立師範学校、1943年に沖縄師範学校と変えました。沖縄師範学校になった際、女子師範学校を併合し、男子部と女子部を置きました。同校の目的は教員養成でしたが「皇国の蜜に即して国民学校教員たるべき者を錬成する」に変わっていきました[琉球新報社会部2014:17]。
【鉄血勤皇隊】
沖縄師範学校男子部386名は、1945年3月31日、鉄血勤皇隊(戦後通称)として動員されました(教員は24名)。動員された部隊は、第三十二軍司令部(通称:本部、千早隊、斬込隊、野戦築城隊、特編中隊)で、動員された場所は留魂壕および第三十二軍司令部壕でした。生徒226名、教員9名の犠牲者数が出ました[琉球新報社会部2014:40][川満2021:76]。鉄血勤皇隊の勤務内容は、次の通りです。宣撫工作(住民への情報伝達)、伝令、弾薬や急造爆雷の運搬、壕掘り、陣地構築、負傷者担送、立哨、看護、雑役、戦闘参加など[琉球新報社会部2014:40]。
学徒隊「鉄血勤皇隊」のほとんどは、その任務内容から以下の3隊に分けられていました。「まず、上級生を中心に、身体強健で意志強固な生徒は『菊水隊』と呼ばれる斬り込み隊に編入された。楠木正成の旗印にちなんで命名されたこの少数精鋭は、文字通り決死の覚悟で敵陣に突入することを期待された突撃部隊で、対戦車用三式手投爆雷や、黄色火薬を箱に詰めた背負い式の急造爆雷を使って、迫り来る敵戦車に肉薄攻撃を行なう訓練を施されていた。二番目の部隊は『千早隊』と呼ばれる通信部隊で、この名称もまた、楠木正成が本拠とした千早城から取られていた。千早隊の学徒は、部隊間の通信を補佐するのみならず、軍司令部から発表される戦況情報を民間人に告知して、県民の戦意を鼓舞する役割を期待されていた。そして、人員規模が最も大きかったのは、三番目の野戦築城隊だった。この部隊は、司令部をはじめ首里攻防戦の陣地構築や弾薬運搬など、日本軍の人手不足を補う上で欠かせない『補助兵員』であり、戦争中は休む暇もなく壕掘りなどの肉体労働に追われていた」[山崎2005:183]。鉄血勤皇隊は6月18日に解散を命じられました[山崎2005:184]。解散命令が出された後の学徒の行動は、「北部の日本軍と合流すればまだ戦えるという情報に従い北部を目指す」「南部をさまよう」「斬り込み攻撃に出される」「捕虜となる」など様々でした[吉浜忍ほか2019:121]。
【教育勅語】
教育勅語は、戦前の日本の教育理念を示したものです。天皇のことばとして1890年に発布されました。天皇への忠義と親への孝行を意味する「忠孝」が求められ、天皇が「日本の家長」であり国民はその「赤子」であるとしています。小学校高学年から暗唱させられました[ひめゆり平和祈念資料館資料委員会2004:21]。
【捕虜になることが困難であった状況】
沖縄戦では捕虜になることは咎められていました。まず、それを示すいくつかの民間人の証言例を紹介します。
伊佐順子氏(中城村仲順住民。当時12歳。玉城村前川から具志頭与座・仲座へ移動):「私は、玉城村の前川で、斬り込み隊に行く日本軍の口から、『中部で捕虜になった人たちは、子どもは股を裂いて皆殺しにされている。そして女は米軍の玩具にされている』と聞かされていました。だから、どんなことがあっても捕虜にはならないと両親に言い続けておりました」[行田2008:575]。
宮良ルリ氏(元ひめゆり学徒):「戦争の時は軍隊の戦陣訓(行きて虜囚の辱めを受けず)が国民の中に浸透していたのである。当時私達は、国の為に潔く死ぬのだと言われ、またそう信じていた」[青春を語る会2006:299]。
なお、多くの日本兵も、捕虜になることをよしと考えていませんでした。米国陸軍省側の記録では、次の通り、自決する兵もしくは死ぬまで戦う兵が多かったことが伝えられています。「ヨーロッパでの戦争と、太平洋戦争との大きな相違点といえば、沖縄戦の例でもわかるとおり、太平洋戦争では、軍人の捕虜が少ないということだった。5月末までに、米第3水陸両用運(北部戦線)が捕虜にした日本兵は、わずか128人。また沖縄南半分での2カ月にわたる戦闘で、第24師団、第4師団の捕虜は、わずか90人、第7師団は、4月の末日から5月にかけて沖縄の中央部戦線で戦ったが、その期間中の捕虜はたった9人しかいなかった。しかも捕虜になった日本兵のほとんどは、重傷で動けなかったか、あるいは意識不明になっていたために、自然捕虜にならざるをえなかったのである。さもなければ彼らは、米軍に降る前に自殺をとげたのである。(中略)彼らは殺されるまで戦ったのだ」[米国陸軍省1968:207]。
【牛島満】
第32軍司令官。1937年11月の南京包囲戦では、第36旅団長(熊本の第6師団所属)として参加し、追撃戦を指導しました[藤原1987:83]。牛島は、1945年5月22日首里司令部壕から摩文仁へ移動することを決定し、5月27日に壕を出て、5月29日摩文仁の丘に到着しました[石原1984:226]。6月18日、第32軍最後の文書による命令書を出し「鉄血勤皇隊をひきいて部隊の戦闘終了後はゲリラ戦にでよ」と一将校を、その指揮官に任命しました[米国陸軍省1968:254]。6月23日、「最後まで敢闘し、生きて虜囚の辱めを受くることなく、悠久の大義に生くべし」と最後の言葉を残して自決をしました[石原1984:227]。
牛島は幕僚畑を歩いたエリートでしたが、反東条閥であったため、第一戦兵団長として北支を転々とした後、沖縄へ飛ばされたようです[濱川1990:90]。
牛島を司令官とする日本軍は、1945年4月24日、首里周辺の非戦闘員に、首里以南(沖縄本島南部)へ移動することを命じました。その時点では北部への疎開が困難になってしまっていたので、住民は首里以南へなだれこみ、墓や自然壕などに避難することになりました。5月末頃から守備軍の南下が始まると、南部は軍民混在の状態になりました。その結果、戦闘の邪魔になるという理由で、軍人が住民に被害を与えるということが起きました。例えば、①住民を避難壕から砲煙弾雨の中へ追い出す、②軍民雑居の壕内では、泣き声で敵に居場所が知られてしまうという理由で、泣く赤子や幼児を毒殺・絞殺・軍刀による刺殺を行う、などの悲劇が数多く起きました。また、②と同様の理由で、日本兵に殺されるよりはと、母親が自らの手で愛児を殺すということも起きました[石原1984:227]。
【長勇】
第32軍参謀長。若い頃、桜会急進派で十月事件(1931年のクーデター計画)に関与しました[藤原1987:83]。上海派遣軍司令部の情報主任参謀(中佐)として南京攻略戦に参加した際、指揮下の師団から、捕虜をどうするのかという問い合わせに「ヤッチマエ」とくりかえし命令していたことが知られています[林2010:38]。
長勇は、東条英機に睨まれた反東条閥の1人で、サイパン島守備軍参謀長として赴任する予定でしたが、同島が陥落したため死を逃れることができました。しかし、その後、東条により沖縄へ赴任させられました[濱川1990:89-90]。長勇参謀長の沖縄県民に向けた言葉が1945年1月27日付『沖縄新報』で次のように紹介されています。「個人の権利とか利害などを超越して神州護持のため兵隊と同様、すべてを捧げること」「我々は戦争に勝つ重大任務遂行こそ使命であれ、県民の生活を救うがために負けることは許されるべきものではない」「県民の戦闘はナタでも鍬でも竹槍でも身近なもので軍隊の言葉でいう遊撃戦をやるのだ。県民は地勢に通じており、夜間の斬り込み、伏兵攻撃即ちゲリラ戦を以って向かうのである」[行田2008:203]。長勇参謀長は、陽気で破天荒な面を持っていました。『私の沖縄戦記』では、次のようなエピソードが記されています。
・「参謀長の部屋では終日、賑わいを見せていた。ウイスキー瓶を片時も手放さない参謀長を取り巻いて、いろんな人々の出入りが激しく、時には女を入れてみるに耐えない痴態を繰り広げることもあった」[濱川1990:89]。
・5月4日の総攻撃に失敗して以来、「虚無感から抜け出そうとするかの如く朝からアルコールびたりであった」[濱川1990:128]。
・摩文仁の軍司令部壕の参謀長室では、アルコールの臭いがただよい、豪快な笑いが絶えなかった[濱川1990:170]。
【黎明の塔】
第32軍司令官・牛島満と参謀長・長勇が祀られている、摩文仁にある塔。1952年建立され、1962年改修されました[大田1985:103]。
【第62師団(石部隊)】
第62師団は、1943年6月に華北で編成されて以来、京漢作戦(1944年4月開始。大陸打通作戦ともいう)など数々の中国大陸での作戦に参加してきた多くの実戦経験と侵略経験を有する部隊でした[藤原1987:64]。
第62師団(師団長・藤岡武雄中将)は、1944年7月第32軍に編入され、1944年8月中国大陸から沖縄へ移動しました。1944年11月まで第24師団(山部隊)と第9師団(武部隊)の中間地帯(とくに浦添付近)の防備につきました。第9師団の台湾への転任後、1944年12月、首里西北部の防備を主任務とし、同時に知念半島の防備にもあたるようになりました。1945年2月、第62師団配下の独立歩兵第12大隊(賀谷支隊)は中(嘉手納)飛行場周辺に配備されるようになりました。その結果、知念半島の防備は、独立混成第44旅団(球部隊)が受け持つようになりました。なお、第32軍司令部が首里を放棄して摩文仁へ撤退するのに伴い、第62師団は津嘉山へ移動しましたが、6月中旬、喜屋武半島に押し込まれる形となり、6月22日師団長藤岡武雄中将は摩文仁で自決しました[大田1985:106-107]。
【三光作戦(石部隊関連)】
三光作戦(三光政策ともいう)は、日本軍が華北で行った掃討作戦に対する中国側の呼称です。掃討作戦は、中国共産党と八路軍(華北の中国共産党軍)が指導する抗日根拠地・抗日ゲリラ地区とその周辺に対して行われました。三光とは、中国語の殺光(殺しつくす)、搶光(奪いつくす)、焼光(焼きつくす)の意味です[岡部2010:97]。2005年、中国の撫順および太原戦犯管理所に収容されていた戦犯45名の自筆供述書が中国側から中国帰還者連絡会に提供されましたが、その中には、三光作戦に関わった10名の将校の証言もあります[岡部2010:97]。また、その将校の中には、独立混成第4旅団第13大隊教育主任・住岡義一も含まれています。独立混成第4旅団は、後に同旅団と独立混成第6旅団を基幹として、第62師団(石部隊)となりました[岡部2010:98、114]。
独立混成第4旅団は、北支那方面軍隷下の第1軍に所属。独立混成第4旅団の「第一期晋中作戦戦闘詳報」(防衛研究所図書館所蔵)によると、第1軍参謀長田中隆吉少将は、山西省中部の晋中における掃討作戦の際「敵根拠地を燼滅掃蕩し、敵をして将来生存する能わざるに至らしむ」と指示しました[岡部2010:104]。また、同詳報には、「敵根拠地に対し、徹底的に燼滅掃蕩し、敵をして将来生存するに能わざるに至らしむること緊要なり、之が為無辜の住民を苦ましむるは避くべくも、敵性顕著にして敵根拠地たること明瞭なる部落は、要すれば焼棄する又止むを得ざるべし」という独立混成第4旅団旅団長・片山省太郎の指示も記されています[岡部2010:104-105]。
また、住岡義一の自筆供述書には、次の通り、現地女性を拉致・拘束して、日本兵に強姦させたという内容の記述があります。「1943年1月中旬より同年3月下旬迄、私は部下森軍曹に命じ兵力を以て(中略)合計7名の婦人を拉致して来て、分遣隊前の家屋内に拘置してこれを隊の慰安所とし1月より3月の間部下をして自由にここに行って強姦させた」[岡部2010:131]。
日本が軍事占領した山西省は、鉱物資源に恵まれ、現在でも中国の3分の1の埋蔵量を占める石炭を有しています。また、鉄鉱石も省内の同省の各地で産出。さらに、銅や石灰、硫黄、ボーキサイト、岩塩などの重要鉱物資源もあります[岡部2010:113]。日本は、山西省太原の中国人の製鉄所を接収して、太原製鉄工場と名付けました。また、河本大作社長の国策会社・山西産業株式会社に製鉄生産を運営させました。そして、山西省陽泉の製鉄工場を、大倉財閥系列の大倉鉱業株式会社に操業させました[岡部2010:113]。さらに、日本軍は、収奪した鉱物資源を運び出すために、国策会社・華北交通株式会社に鉄道網の整備と経営をさせました[岡部2010:113]。アジア太平洋戦争が始まると、山西省の資源の収奪と輸送はますます重要となり、その体制を維持するために、太原に司令部を置く第1軍は、抗日根拠地や抗日ゲリラ地区に対する掃討作戦を繰り返し行いました[岡部2010:113]。
【戦時教育】
満州事変(1931年)以降、「15年戦争」が始まりましたが、それ以降、皇民化教育はそれまで以上に力が入れられるようになりました。日本政府は1932年に国民精神文化研究所を設立し、全国から指導的な教員を集めて教育し皇国思想を吹き込みました。その際、沖縄からは沖縄師範学校女子部の仲宗根政善氏などが派遣されました。政府は、1935年国体明徴運動(天皇を絶対化・神格化)、1937年国民精神総動員運動を起こしました。1937年4月には、文部省は『国体の本義』を発行しました。教員は、そうした思想を教え込む者として教育されました[吉浜忍ほか2019:129]。
1941年4月、「国民学校令」により、小学校は国民学校になりました。小学校教育の目的は「皇国の道に則って、基礎的錬成(心身を鍛える)を行なうこと」とされ、以後、教育は急速に軍事化されていきました[吉浜忍ほか2019:130]。1943年6月、「学徒戦時動員体制確立要綱」が閣議決定され、各学校に「一 有事即応態勢の確立」「二 勤労動員の強化」と、生徒の役割が提示されました。生徒たちは「食料増産、国防施設建設、緊要物資生産、輸送増強等に(中略)積極協力」する者とされました。1944年、沖縄に第32軍が創設されると、「二 勤労動員の強化」は顕著に表れるようになりました[川満2021:55]。1944年1月、現在の県教育長にあたる県視学は、新聞紙上で「皇国護持のために死ねる皇国民の錬成にその根本義があることを我々実際家は肝に銘ずるべきである」と発言しました[吉浜忍ほか2019:131]。
瑞慶覧長方氏(沖縄戦時12歳。大里村)は、戦前の教育を振り返ってこう述べています。「日本人というのは万世一系、天皇の臣民だということ、日本は神の国で、アメリカとかイギリスは鬼畜生(鬼畜米英)だから、それに勝つためには心一つにして『一億一心うちてしやまん』という標語で戦うという教育です。そして、天皇陛下のためには命を捨てることを、『死ぬものも美徳である』というふうに徹底して教えるんだね。(中略)『大舛大尉に続かん』という美化したスローガンを作って徹底的にやるんですよ。(中略)教育勅語なんか意味分からんのに、全部暗唱させる。そういう教育でしたよ。(中略)尋常高等小学校という名前から国民学校に変わると(中略)教科書自体も全部変わりました。(中略)社会科の本は『南方には資源がいっぱいある』『日本の力でもって開発して全部大東亜共栄圏を作って、夢の国をやるんだ』と、こういうふうに、すべて教科書の内容を変えました」[行田2008:179]。
【終戦直後の教育】
戦後、米軍により、民主主義教育が導入されました。『沖縄戦を知る事典』では、軍国主義教育・皇民化教育と異なる教育に移行した当時の状況について、次のように説明されています。「多くの教員たちは躊躇なくそれを受け入れ、『軍国教師』から『民主主義教師』へと変身していった。生徒の中にはそのような変身ぶりに反発を覚える者もいたが、誰もが生きることに精いっぱいという時代の中では、大きな波紋とはならなかった」[吉浜忍ほか2019:132]。湧上洋さんも、筆者の取材の際に、「戦後まもなくは、生活することだけで精一杯だったので、それ以外のことを真剣に考える余裕はありませんでした」と述べています。
なお、戦後、戦時教育に憤りを覚えるようになった伊佐順子氏(沖縄戦時12歳)はこう述べています。「昔の私たちの学校教育は、常に親に孝行して、天皇陛下のために恩義を尽くして、国のために尽くせる人間になれと教えこまれました。その教育が人間形成の上で大変大きな役割を果たしました。(中略)戦後、いろんなことを勉強しながら、日本の教育のあり方が間違っていたことを思い知らされたときは、本当に残念で、憤りを感じました」[行田2008:576-577]。また、瑞慶覧長方氏(沖縄戦時12歳。大里村)は、こう述べています。「もっとも犠牲をこうむったのが弱い住民でした。特に何にも知らない学生は、学校では皇民化教育で洗脳され、友軍といって軍隊に協力させられ、あげくの果てに完全に裏切られたわけです。正直言って戦争が終わった時、本当の意味の空しさというんですか、何を信じたらいいのか、教育とは何だったのかと、ものすごい教育不信に陥りましたね[行田2008:593]。
【日本への経済制裁】
米英は、中国に対して軍事物資を支援していました。中国に進出を行っていた日本軍はその支援ルートを断ち切る目的で、仏印(フランス領インドシナ)へ進出しましたが、米国等から経済制裁を受けることになりました。まず、日本軍は1940年9月23日北部仏印に進駐。それに対する制裁として、米国は、1941年7月25日、在米日本資産を凍結し、26日には英国、27日には蘭印もこれにならいました。
しかしながら、制裁のかいなく日本軍は1941年7月28日、南部仏印に進駐しました。その結果、制裁は強化されました。まず、蘭印が7月28日、日蘭民間石油協定を停止しました。8月1日には、米国が対日石油輸出の全面禁止をおこないました。これらは、南部仏印進駐が日本の本格的な南方への武力進出の準備であるとみなしての経済制裁措置でした。日本側は米国が南部仏印進駐でこのような強硬な経済報復措置をとるとは真剣に考えていませんでした[大江1991:85]。
1941年8月17日、野村駐米大使は、ルーズベルト大統領から直接警告を受けました。日本が仏印から撤退し仏印の中立宣言に参加するという米国の提案を受けいれないかぎり交渉の可能性がない、と言われました。さらに、「若し日本国政府が隣接諸国を武力若くは武力的威嚇に依り軍事的支配の政策又は『プログラム』遂行の為め更に何等かの措置を執るに於ては」、米国「政府が必要と認むる一切の手段を講ずる」と、強く威嚇されもしました[大江1991:89]。
【南進政策】
1940年7月に成立した第2次近衛内閣は、組閣直後に「基本国策要綱」を閣議決定しました。その中で「大東亜新秩序の建設」が打ち出され、中国支配構想が提唱されました。閣議決定の翌日、大本営政府連絡会議は、大本営陸海軍部案の「世界情勢の推移に伴う時局処理要綱」を決定しました。これにより初めて、国策レベルで対米英戦争が想定されました。この「要綱」では、仏印(仏領インドシナ)の基地強化が目標とされました。また、南進政策の公式採用も明記されました[纐纈1999:97-98]。
1940年9月、日本は北部仏印に武力進駐を強行しましたが、報復措置として米国から屑鉄の全面禁輸の経済制裁を招くことになりました。
1941年7月2日には「情勢の推移に伴う帝国国策遂行要綱」が御前会議で決定され、南進政策の遂行のためには「対英米開戦を辞さず」という方針が確認されました[纐纈1999:99]。そして、7月28日、日本軍は、南部仏印進駐を実行しました。
なお、南進の目的について、「大陸命」(天皇から陸軍参謀本部長に勅命を下した機密文書)第五六四号(1941・11・15)に「占領ノ治安ヲ恢復シ重要国防資源ヲ取得シ且軍自活ノ途ヲ確保スル為占領地ニ対シ軍政ヲ施行ス」と記されています。この勅命は参謀総長杉山元の名で前線司令官に伝達され「重要国防資源の急速獲得」の実施要領が徹底されました[色川1998:31]。
また、1941年12月12日(開戦直後)に関係大臣会議で決定された「南方経済対策要綱」では、「開発ノ重要ヲ石油ニ置」き、さらにニッケルやボーキサイト、クロム、マンガン、雲母、燐鉱石、その他の特殊鋼原鉱、非鉄金属などの開発をすすめること、そしてそのために「極力在来企業ヲ利導協力」させることが記されています[林1999:37]。取得することが期待される資源は、大本営陸軍参謀本部が作成した「南方作戦ニ伴フ占領地統治要綱」(1941年11月25日)でも、見ることが出来ます。その資源は、①フィリピンからマンガン、クロム、銅、鉄鉱、マニラ麻、コプラ、②英領マラヤからボーキサイト、マンガン、鉄鉱、スズ、生ゴム、コプラ、タンニン材料、③英領ボルネオから石油、④蘭印から石油、ニッケル、ボーキサイト、マンガン、スズ、生ゴム、キナ皮、キニーネ、ヒマシ、タンニン材料、コプラ、パーム油、工業塩、とうもろこし、となっています[林1999:37]。
池宮城秀意1970『沖縄に生きて』サイマル出版会
石原昌家1984『証言・沖縄戦』青木書店
色川大吉1998『近代日本の戦争』岩波書店
上羽修1999『母と子でみる44 ガマに刻まれた沖縄戦』草の根出版会
大江志乃夫1991『御前会議―昭和天皇十五回の聖断』中公新書
大田昌秀1985『沖縄戦戦没者を祀る慰霊の塔』那覇出版社
岡部牧夫ほか編2010『中国侵略の証言者たち』岩波書店
柏木俊道2012『定本 沖縄戦』彩流社
川満彰2021『沖縄戦の子どもたち』吉川弘文館
葛原和三2005「南部への後退後に激増した軍民の損害 第32軍、首里撤退の是非」『沖縄決戦 Okinawa the last battle』(歴史群像太平洋戦史シリーズ 49)学習研究社
纐纈厚1999『侵略戦争』筑摩書房
行田稔彦(編著)2008『生と死・いのちの証言 沖縄戦』新日本出版社
青春を語る会(編著)2006『沖縄戦の全女子学徒隊 次世代に遺すものそれは平和』フォレスト
仲宗根政善2015(1982)『ひめゆり塔をめぐる人々の手記』KADOKAWA
濱川昌也1990『私の沖縄戦記』那覇出版社
林博史1999「「大東亜共栄圏」の実態―日本軍占領下のアジア」沖縄県文化振興会公文書管理部市史編集室編『沖縄戦研究』2沖縄県教育委員会pp.35-62
林博史2001『沖縄戦と民衆』大月書店
林博史2010『沖縄戦が問うもの』大月書店
ひめゆり平和祈念資料館資料委員会執筆・監修2004『ひめゆり平和祈念資料館 HIMEYURI PEACE MUSEUM official guide book』沖縄県女師・一高女ひめゆり同窓会
藤原彰(編著)1987『沖縄戦―国土が戦場になったとき』青木書店
米国陸軍省(編)、外間正四郎(訳)1968『日米最後の戦闘』サイマル出版会
山崎雅弘2005「戦争に組み込まれた二つの学徒隊」『沖縄決戦 Okinawa the last battle』(歴史群像太平洋戦史シリーズ 49)学習研究社
吉浜忍ほか(編)2019『沖縄戦を知る事典』吉川弘文館
読売新聞戦争責任検証委員会2006『検証 戦争責任』1中央公論新社
琉球新報社会部(編)2014『未来に伝える沖縄戦』3琉球新報社 琉球新報社会部(編)2015『未来に伝える沖縄戦』4琉球新報社