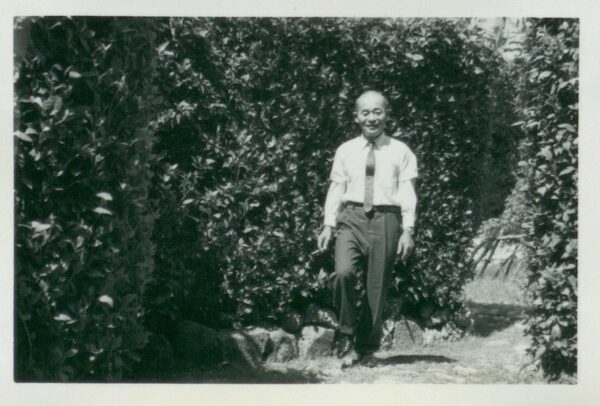
【資料群紹介】上原清光コレクション
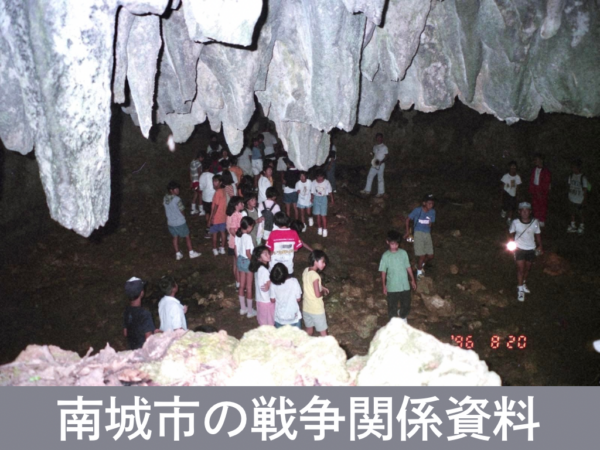
南城市の戦争関係資料リンク集

日本復帰前の南城市の産業 ―統計調査による検討―
私たちの社会がどのように歴史をたどっていまのような姿になったのか。この問いを考えるための方法はいくつかあります。まず一つは、実際にその歴史を生きてきた人に語ってもらうことです。私が沖縄国際大学で担当するゼミの学生にさせたのも、このやり方です。いろいろな方から、その方たちがどのように生きてこられたのかについてお話しを聞かせてもらい、想像する。そのようなことを通して、具体的な形で歴史を体感するとともに、歴史とは身近なもので私たち一人一人もそれを構成するのだというところも感じてほしいと願い、学生を送り出しました。皆さまのご協力もあり、この目的は十分に達せられたと考えています。
学生らの調査レポートについては、以下のリンクからご覧になれます。
| レポート | 調査者 | |
| 1 | 奥武島 | チームA(井上成、岸本陽太、呉屋凱斗、仲間麗桜) |
| 2 | 株式会社 南都 | チームC(大城吏功、中山志帆、日賀雄太郎、山城遙) |
| 3 | チャーリーレストラン | チームB(太田さき、楚南美月、長嶺瑠依、長谷川志央) |
さて、今回は、もう一つの有力なやり方で南城市の歴史に接近してみましょう。それは、統計を使う方法です。「国家の存するところ統計あり」(19世紀フランスの統計学者・モーリス・ブロック)という言葉もあります。どの時代のどのような国家であっても、社会や経済の状況を捉えるために統計を必要とします。戦後アメリカ統治下に置かれた沖縄であっても同様で、当時の琉球政府もいろいろな統計調査を実施しました。そのような統計調査のデータを使うことで、当時の社会経済の状態についてたくさんの情報を得ることができます。
今回利用するのは、日本復帰直前の1970年に実施された「事業所基本調査」という調査です。この調査は、1970年8月1日時点での沖縄中の“すべての”事業所(事業所というのは、大雑把にいえばお店や会社などのことです)を対象として、どのような事業をしていて、メインに取り扱っている商品やサービスはなんなのか、どれくらいの従業員がいるのか、いつから事業を始めたのか、などを聞き取ったものです。膨大な量のデータになるので、今回は、現・南城市域のうち旧玉城村に焦点を絞り、この統計調査から当時の社会経済の姿を描き出してみたいと思います。
玉城村の分析に移る前に、まずは、戦後から日本復帰に至るまでの沖縄経済全体の流れを概観しておきましょう。
沖縄県は苛烈な沖縄戦によって、経済も壊滅的な打撃を受けました。県民の4分の1が亡くなるという激戦のなかで、生き残った人びとの多くも家や働く場所を失い、工場などの生産設備もかなりの部分が破壊されました。不発弾があちこちに埋まっている中では耕作することも命がけで、人びとの生活は困難を極めました。
1950年代に入ると、恒久的な米軍基地建設が本格化しました。基地建設に投下される莫大な資金によって経済復興は果たされましたが、その過程で、卸売・小売業やサービス業などの第3次産業の就業者や所得が著しく増大しました。また、日本本土やアメリカなどからの輸入額が拡大し、輸出額をはるかに上回るようになりました。そこでの「貿易赤字」は、基地関連収入によって補われました。このような経済の形を、「基地経済」といいます。
1950年代後半から日本本土復帰前の1970年代初めまで、高度経済成長ともいえる時代が訪れました。1955~71年度にかけての成長率は年当り13.4%に達しました。この水準は、同時期に高度成長を享受していた日本本土の成長率15.6%に全く遜色がないほどの高さです。高度経済成長の主要因は、基地関連輸入の拡大でしたが、その他にもいくつかの要因がありました。1956~57年度には、日本本土の鉄くずの原料不足を背景として、「スクラップ・ブーム」がありました。1958~62年度には、日本本土の企業と連携して、沖縄内で大型の製糖工場が相次いで建設され、「サトウキビ・ブーム」が起こりました。1960年代中頃には、ベトナム戦争へのアメリカの本格的介入により特需(ベトナム・ブーム)がもたらされるとともに、このころから、日本政府による財政援助が大幅に増額されるようになりました。
「高度経済成長」のなかで、沖縄の経済社会は大きく変容しました。図表2−1で、1960年から1970年にかけての産業別就業者の推移を見てみましょう。この図表によれば、1960年時点では、沖縄全体で働く状況にあった人38万3千人のうち、17万5千人(全体の45.7%に相当)もの人が農林業に従事していました。ところがこの人数・シェアのその後を見ると、1965年には14万5千人(同36.4%)、1970年には10万人(同25.7%)と急激に低下しました。その代わりに就業者を増加させたのが、建設業(1万8千人増)や卸売・小売業(1万8千人増)、そしてサービス業(1万9千人増)です。この十年間で、沖縄経済は脱農業化・サービス産業化が一挙に進み、いま私たちの生きているような社会の姿にぐっと近づきました。
-1.png)
いよいよ、「事業所基本調査」を使って当時の経済の実態に迫りたいと思います。「事業所基本調査」では、沖縄全体で4万3205件の事業所を調査しました。図表3-1で示すように、産業別でみると、最も多かったのが「卸売・小売業」で2万8189件(65.24%に相当)、次いで「サービス業」が9513件(22.02%)でした。
このうち、現・南城市域(旧玉城村、旧知念村、旧佐敷町、旧大里村)では、684件の事業所が調査されました。図表には出していませんが、旧4町村別の内訳では多い順に、旧玉城村244件、佐敷町213件、知念村127件、大里村100件でした。現・南城市域の事業所の産業をみると、「卸売・小売業」448件(65.50%)、「サービス業」20.91%の順でした。沖縄全体での傾向と合致していることが確認できます。
.png)
ここからは、旧・玉城村の事業所に絞り込んでみていきます。まずは調査対象事業所244件の字別の内訳を、図表3-2で示しました。最も多い順に、親慶原40件、百名33件、富里29件でした。
ただし、公文書館に残されている資料で筆者が確認した限り、旧・玉城村の簿冊には243件分の調査票が残されていますが、うち27件分は伊平屋村のものが紛れ込んだものでした。したがって、旧・玉城村については確認することができた216件分のデータのみ用いることにします。
この216件についての代表的な業種別に内訳をみたものが、図表3-3です。この表では、該当する事業所が3件以上あるような業種を抜き出しています。これをもとに、いくつかの業種を取り上げ、その特徴を紹介します。
旧玉城村で最も多かった業種は小売業(雑貨など)で84件(全体の38.89%)でした。扱っている品目についての回答では、米、缶詰、菓子、飲物、タバコが多く挙げられていました。食に関係するものが多かったようです。酒類を挙げた店も12件ありました。小売業(雑貨など)は店主(事業主)が一人で営んでいる店がほとんどでした。
次いで多かった新聞取次所は、琉球新報と沖縄タイムスがそれぞれ設置されていましたが、両紙を同時に扱うところもありました。事業主とその家族を中心に、新聞の申し込みを受け、配達を行っていました。
運送業では、全ての事業所が事業主1名のみで運営していました。トラックなどで荷物の運送を手掛けていたようです。1件のみ、「コーラル」(サンゴ砂利のこと)の運搬が主な内容であると回答していました。また、11件のうち10件の事業所で、開設時期が1965年以降でした。比較的新しい業種であったといえます。このころに人びとの所得が上昇し自動車の普及が進んでいったことが示唆されます。
小売業(鮮魚)では、扱っている魚の種類を回答している事業所もありました。それによれば、さば、まぐろ、たこ、あじ、カツオなどが売られていたようです。また、小売業(精肉)と合わせた18件のうち7件では魚と肉の両方を扱っていました。
砕石業では、「あわ石」「玉石」などを採集していたようです。「あわ石」とは、粟石(あわいし)のことで、「海にすむ有孔虫の殻、石灰岩・貝殻などの欠片が固まってできた石灰砂岩で、色や形が〈あわおこし〉に似ているのでそう呼ばれる。沖縄本島南部に分布し石材として使われる」そうです(『最新版沖縄コンパクト事典』)。事業所名に「コーラル」が入っているところも2件あり、先の運送業でコーラルの運搬が主な内容であると回答した事業所とは何らかのつながりがあったのかもしれません。また、8件のうち5件で常雇の従業員がおり、最大で9名も雇っている事業所もありました。なお、土木工事業や木造建築工事業ではさらに大規模で、従業員が20名を越す事業所もありました。製造業・建設業が地域の人びとに働く場を提供していたことが伺えます。
食堂は4件で、確認できる限りでは、「そば」「みそ汁」などを提供していたようです。近い業種としては、料亭が1件、パーラーも2件ありました。
なお、「事業所基本調査」には、他にも調査項目があります。例えば「販売先別割合」について、事業所の販売先が、1)沖縄内、2)観光客、3)外人、4)輸出のそれぞれに何%くらい仕向けられるのかを聞いています。旧玉城村の場合、2)観光客と4)輸出を回答した事業所は全くありませんでした。3)外人では、20%と5%という回答がそれぞれありました(ちなみに前者は自動車整備業で、後者は駐車場経営でした)。観光客や米軍施設の従業員というよりは、ほとんどが地元の住民向けの事業であったことがわかります。
これまでの分析をとおして、復帰直前の旧玉城村の産業について具体的なイメージが湧いて来たでしょうか。第2節で概観したように、1950年代半ばから1970年ごろというのは、高度経済成長のなかで沖縄の経済社会の形が大きく変わった時期でした。旧玉城村もその流れのなかで、卸売・小売業やサービス業が相当なウェイトを持っていたということが分かったかと思います。他方で、農業や漁業についてもこの間に大きな影響があったかと思いますが、それらは「事業所基本調査」の対象に含まれないため、今回の分析では見えてきませんでした。農業については、1971年には「農業センサス」というすべての農家を対象とした大規模な調査が実施されますので、そのデータを分析することによって、旧玉城村(ひいては現・南城市域)の経済社会の姿をよりクリアに浮かび上がらせることができると思われます。今後の課題とします。
最後に、今回の論考のようなアプローチが面白いと感じられた方に向けては、加藤政洋先生による研究を参考資料のなかでご紹介しておきます。「事業所基本調査」を活用して当時のコザの通りを復元しています。関心を持たれた方は、ぜひご覧ください。
【参考資料】
〇刊行資料
・加藤政洋(1970)「基地都市コザにおける歓楽街「センター通り」の商業環境 : 1970年「事業所基本調査」の分析から」『立命館文學』649号
・琉球新報社(2003)『最新版沖縄コンパクト事典』琉球新報社
〇未刊行資料
・「事業所基本調査 事業所調査票 1970年 玉城村」(琉球政府企画局統計庁、沖縄県公文書館所蔵、資料コード:R00007707B)
・「事業所基本調査 調査区要図・調査対象名簿 1970年 玉城村 001~036」(琉球政府企画局統計庁、沖縄県公文書館所蔵、資料コード:R00007705B)
・琉球政府企画局『第15回沖縄統計年鑑 1970年』