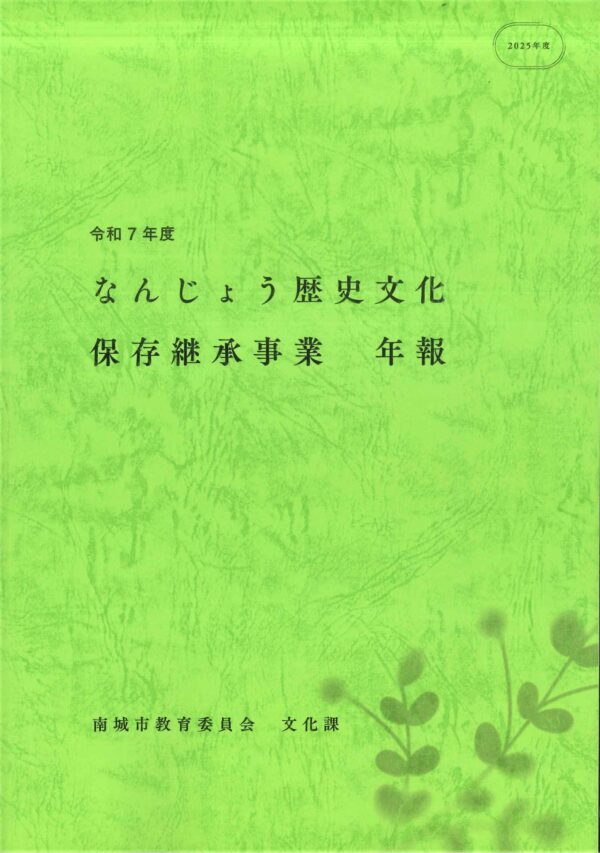
【年報】『なんじょう歴史文化保存継承事業 年報』

【レポート】親子向け歴史講座「南城市の戦争遺跡」
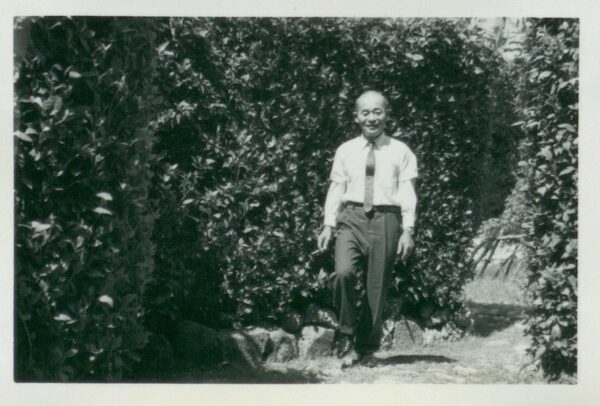
筆者は、なんじょうデジタルアーカイブを立ちあげる際、地方自治体のデジタルアーカイブのあり方について考えました。まずは、ほかの地方自治体のデジタルアーカイブを参考にすることにしました。3年ほど前の話です。筆者は、アトランダムに、国内の約100のデジタルアーカイブを見て、次の3つの感想を抱きました。
・見た目のよい資料や、郷土の誇りになるような資料だけが選択されて公開されている。
・情報の多様性が薄い(「情報の多様性」については、「多様性とデジタルアーカイブ①」を参照)。つまり、多種多様な情報が大量に公開されているとは言えない。
・インターネットで世界に配信している割には、その地域の外の世界とのつながりが意識されていない。
そして、筆者は、歴史家・金城正篤氏の言葉を思い出しました。金城氏は、1975年に沖縄県内の郷土史の問題点と課題について次のように論じました。
その土地の物産として「砂糖」をとりあげる場合でも、たんに年度ごとの生産高を掲げるだけでは不十分であろう。王府時代はもちろん、廃藩置県以後も(あるいは地方では今日においてさえ)、農村のほとんど唯一の換金産物たる砂糖の生産が、いかなる生産関係のもとでどのようにおこなわれたか、また、沖縄経済全体もしくは日本資本主義経済の最底辺として、いかな地方的特質を付与されていたのか、といったようなことが指摘されていなければならないだろう。(中略)わたしの見ることのできた史・誌の多くは、上にのべたようなことがらについてはほとんどふれられていないのが実情である。これでは「お国自慢」的なたんなる物産紹介か、郷土案内ではあっても、歴史とは無縁である。
金城正篤1975「「郷土史」編纂の現状と問題点」『新沖縄文学』28号 新川明(編) 沖縄タイムス社pp.205-206
筆者は、「沖縄経済全体もしくは日本資本主義経済の最底辺として、いかなる地方的特質を付与されていたのか」という箇所に注目します。これには、重要な指摘が2つあると言えます。1つ目は、視野を広く持ち、その地域の外との関係性を論じる努力が必要であるということ。2つ目は、ネガティブな点(ここでは、「日本資本主義経済の最底辺として」とある)も触れなければならないということです。筆者は、この2つを意識しながら、「インターネットという、世界に発信するツールで、地域の情報を公開することにどのような意味があるのか」を考えるようになりました。本稿では、その問いに答えるべく学習した結果を紹介します。
なお、本稿は、2023年7月21日に公開した「多様性とデジタルアーカイブ①」の続編で、「多様性を高めるためのデジタルアーカイブの構築」を大きなテーマとしています。前編では、「多種多様な情報を大量に公開することで、デジタルアーカイブを多様化するべきである」と主張しました。後編の本稿では、前編の主張をふまえた上で、金城氏の見解を応用して、主に次の2点を主張します。
・地域資料を世界の公共財産とみなして、世界に発信するべきである。
・対立する双方の情報を扱うことにより情報の多様性を高めるべきである。
筆者は、歴史に関わる情報を扱う際、多元的に考察することが必要と考えています。建設物や風景も、見る角度により違って見えます。様々な角度から見ることで、理解が進みます。それと同じで、出来事や人物も、多面的にみることにより、より正しく理解できるようになります。よって、情報は多様であることが好ましいと筆者は考えます。本稿では、情報の多様化の1つの方法として、ネガティブな情報を扱うことが特に重要であるということを説明します。
なお、ネガティブな情報を扱うことは避けられがちですが、本稿では、前向きな気持ちで、ネガティブな情報を「世界の公共財産」とみなして積極的に収集・公開するべきであると、訴えます。その点が本稿の大きな特徴となっています。
第1章では、地方自治体の地域情報を、世界の共有財産として考えるべきであると述べます。第2章では、世界で利用者を増やすための工夫について述べます。第3章では、デジタルアーカイブを運営する責任について考え、ポジティブな情報だけでなく、ネガティブな情報も公開することの重要性について述べます。これは、「お国自慢」的アーカイブからの脱却ということも意味しています。第4章では、3つのテーマを例として取りあげ、第3章の考察を深めます。「さいごに」の章では、全体のまとめをおこないます。
なお、本稿における地方自治体とは、一般的な定義と同様、都道府県または市町村の地方公共団体です。また、地域情報とは、地方自治体単位のデジタルアーカイブで扱われる、その土地の情報です。そして、その情報とは、主に、歴史に関する情報です。歴史の定義は、本稿では「後世に伝えるべき出来事や人、モノ、文化」とします。要するに、地方自治体で価値があるとみなされ記録されている情報全般のことです。
地域情報を世界の共有財産とみなすべきであるという考え方は、歴史家の入江昭氏の主張をヒントにして思いついた考え方です。本章では、入江昭氏の主張を紹介しながら、地域情報を広い視野でとらえることの重要性を述べます。
入江氏は、次の通り、ヨーロッパの例をひいて、歴史の負の遺産を共有財産ととらえるべきであると述べています。
ヨーロッパでは長い間多くの悲惨な戦争があり、海外植民地でアジアやアフリカの人たちを搾取、迫害し、あるいはユダヤ人の虐殺など、悲劇的で反省すべき過去を持っている。そのような事実を史実として認め、ヨーロッパ全体の歴史の暗黒の面だったとする。その一方、ルネサンス、啓蒙時代、あるいは近代市民社会の形成といった誇りうる過去も持っている。そのすべてをフランスもドイツもイタリアも、自分たちの共有財産だとするのである。
[入江2014:141-142]
過去は、国境を超えた「共有財産」である、ということが主張されています。これには、「お国自慢」という閉じられた発想はありません。また、暗い過去も含めて共有財産としているところが特徴的です。
筆者がこの引用箇所に感銘を受けたのは、筆者が「多様性とは何か」を常に考えているからです。多様性がある状態とは、異なる様々な考え方が公平に議論される状態であると、筆者は考えますが、そうは言っても、筆者自身、自分にとって都合の悪いネガティブな情報は、ついつい意識的あるいは無意識的に排除してしまうことがあります。入江氏は、それが私の弱点であることを、気づかせてくれました。つまり、多様性を考えるには、暗い過去(ネガティブな情報)に向き合うことが必要であることを教えてくれたのです。
多様性を高めるためには、ネガティブな見方(批判的な見方)は絶対的に必要です。AとBはよく似ているが少し異なるという状態は多様性の低い状態です。一方、AとBが真っ向から対立する状態(例:核廃絶と核抑止力、環境保護優先と経済発展のための開発優先)は、多様性が高い状態と言えます。異質なものがたくさん同居していればいるほど、多様性が高い状態にあると言えるのです。よって、多様性の高い学習をするためには、暗い過去を直視することや、批判的に論を立てることはどうしても必要になります。
入江氏の主張の素晴らしい点は、暗い過去を嫌々ながら勇気をもって見るというのではなく、我々の共有財産として見るという前向きな姿勢です。誇らしい歴史も、悲劇的な歴史もすべて等しく学ぶ価値のある「地球で起きた歴史の1つ」であると考えれば、人類の共有財産であるとみなすことができるのです。入江氏は、さらに、人類の共有財産という考え方を次のように説明しています。
「歴史解釈」は常に変わりうるものだが、歴史そのものは変えることができない。「歴史を知る」ということは、過去の事蹟を学び、現代とのつながりを考えることである。過去が厳然として存在する以上、それはどの国の人にも与えられた共有財産である。その意味では、人類の歴史はすべて共有されているわけである。
[入江2014:149]。
入江氏は、現在に生きるだれでも、現在とのつながりを考えながら歴史と向き合える、と主張しています。なぜなら、過去に起きた出来事自体は、物理的に変えることができないからです。不変のものは、人類のだれにとっても平等に存在しているのです。
また、入江氏は、「歴史自体は不変」という考え方を、歴史学の研究の潮流を説明しながら、次のように発展させています。
仮に共通した「解釈」がなくても、歴史自体は不変である。その存在を否定することはできない。このような意識が高まれば、アジア・太平洋地域もヨーロッパと同じように、「記憶の共同体」としての自覚が生ずるであろう。
[入江2014:149]
EUは文字通り「記憶を共有するコミュニティ」といわれるわけだが、同じ動きが世界のほかの地域にはありえないということはできない。たとえば、アジア・太平洋地域に住む歴史家のあいだでは、広い意味での「太平洋の歴史」を考える動きが次第に顕著になっている。米国もカナダもメキシコも含め、さらにオーストラリアやニュージーランド、そして数千と存在する太平洋の島々、さらに日本、韓国、中国なども合わせた歴史の流れをたどろうとする動きがある。地域共同体的な歴史を人類の多くが共有するようになれば、それだけ全地球的なネットワークを拡大し、グローバル化の進行しつつある世界を、さらに一層グローバルなものとしていくことになろう。(中略)一国中心の歴史ではなく、すべての人々が共有しうる歴史を学んでいくことが、グローバルな結びつきを一層密接なものとするための根本条件だからである。
歴史を学ぶ、とはそのようなつながりを強化することに他ならない。
幾つかの重要なことが記されているので、筆者の解釈も含めながら、ポイントを整理してみましょう。
・共通の歴史解釈はなくとも、歴史自体は不変である。つまり、起きた出来事自体は、人類の誰もが平等に学習できるものである。それゆえに、世界中の人が、「記憶の共同体」の一員という自覚を持つことができる。よって、世界のどこかで起きた出来事は、世界人類のものであると同時に、自分自身のものでもあると言える。つまり、古今東西のあらゆる出来事は、人類の1人ひとりにとっての共有財産である。
・歴史の研究は、一国中心の歴史の研究だけでなく、グローバルな結びつきが意識されたものであるべきである(歴史研究はお国自慢になってはいけないという金城氏の考え方と軌を一にしている)。
入江氏は、「ある国で起きたことは、ほかの国の人にとっても共有財産である」という趣旨のことを主張していますが、筆者は、この考え方をひろげて、「ある地域(地方自治体レベルの地域)で起きたことは、世界のほかの地域にとっても共有財産である」と主張したいと思います。小さな地域でもデジタルアーカイブを構築してインターネットを利用することで世界中に情報を容易に発信することが可能になった現在、国単位ではなく、地域単位でグローバルな結びつきを考えてもおかしくはありません。それに、すでに、多くの地方自治体が、地域情報をインターネットで発信しています。
地域情報をひろく発信するうえで、物理的障壁がなくなっていることは喜ばしいことです。デジタルアーカイブが普及するまでは、地域史に記されているようなローカル色の強い情報は、特定の地域に限定的に流布している状態にありました。たとえば、市町村が発刊した地域史は、日本全国の図書館に置かれているわけではありません。部数も限られていて、その地域の外では容易に手に入るものではありませんでした。
しかし、近年、状況が変わってきました。地域史をオンラインで閲覧したり、そのデータをダウンロードしたりして利用できるようになってきたのです。世界のどこにいても、地域史を利用できるようになってきました。なんじょうデジタルアーカイブでも、既刊の地域史をPDFでダウンロードできるサービスを提供しています。しかし、まだ、現状で十分であるとは思えません。次章では、地域の情報を、より広く世界に発信するための方法について考えてみます。
前章では、地域情報は世界の公共財産の1つであるという趣旨のことを述べました。本章では、その地域情報を、デジタルアーカイブを通じて世界で広く利用されるようにするための方法を3つ紹介します。1つ目は多言語化、2つ目はテキスト化、3つ目はネットワーク化です。
まず多言語化についてですが、これは、「公開資料に含まれる文(文書資料であれば資料に記された文すべて)」および「その資料の解説文(資料内の文ではなく、資料を紹介するために作成された目録の文)」を、日本語以外の言語でも紹介するというサービスです。地域情報が世界で利用されるようになるためには、世界でもっとも普及している英語を基軸として、多言語で公開されることが望まれます。
「公開資料に含まれる文」および「その資料の解説文」を多言語化したところで、極東の日本のコンテンツが海外で利用されるようになるのか疑わしい、という意見もあるかもしれません。しかし、世界の人々に向けて、地域情報の利用を促す努力をする価値は十分あると、筆者は考えます。なぜなら、コンテンツが多く利用される可能性は実際にあるからです。その理由の1つは、訪日外国人は増加傾向にあるということです。国土交通省のウェブサイトによると、訪日外国人旅行者数は、2003年は521万人ですが、2019年は3188万人となっています。その数は、2020年以降は新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)が世界的に蔓延したために、激減しましたが、日本に関心を持つ外国人が増加している傾向があるということは言えるでしょう。
旅行者は、旅行前、旅行中、旅行後に、訪問先の情報を調べます。特に、実際に旅行してみて感動した時、その土地の歴史や文化を深く知りたくなります。現代では、旅行者は、スマートフォンやタブレットを持ち運びながら、知りたいことをいつでも調べることができます。その際、日本という国全体の情報というよりは、「今訪れている土地の情報」(地域情報)を欲しがります。旅行者のなかには、観光ガイドで書かれている表面的な情報では満足できない人もいます。インターネットで調べた時、情報量が少なかったり、お国自慢的言説だけが垂れ流されていたり、どのウェブサイトの説明も同じような説明がなされていたりすると、ガッカリします(筆者は、そのような経験を多く持ちます)。
しかし、逆に、あるウェブサイトを見つけ、そこに多種多様な地域情報が大量にあったら、どうでしょう。しかも、多言語で利用できたらどうでしょう。利用した旅行者は、感激するに違いありません。そして、その土地の歴史と自国のそれとを比較し、様々な共通点や相違点を見出し、知的好奇心をさらに高めるようになるでしょう。そうなると、その土地のことがますます好きになっていくでしょう。その土地を嫌いになる情報を得たとしても、関心を高めるようにはなるでしょう。これは、情報が「国と国との架け橋」となるだけでなく、「個人と地域の架け橋」にもなるということです。筆者は、このような現象が多く生まれることが、入江氏のいう「記憶の共同体」の構築につがなると考えています。
ここで、筆者は、あらためて多種多様な情報に触れることの重要性を強調します。多種多様な情報に触れると、自分の無知を知り、先入観や固定概念から解放されるようになります。「自分の考えは誤っているのかもしれない」と思って、パニック状態に陥ります。判断を一旦保留(アポケー)せざるをえなくなります。これが知力の向上には欠かせません。一個人が、自身のアイデンティティや歴史性、それまで構築してきた知識をいったんカッコに括って、新鮮な気持ちで、ある国やある地域の歴史に対峙することになります。この態度が、視野を広め、判断能力を高めるようになります。そして、それが可能になる条件が、多種多様な情報に触れるということなのです。
次に、テキスト化について述べます。テキスト化された文字情報は検索でヒットさせることができます。これにはOCRが役に立ちます。OCRとは、「Optical Character Reader(またはRecognition)の略で、画像データのテキスト部分を認識し、文字データに変換する光学文字認識機能のこと」です。例えば、画像として存在している文字情報は、検索してもヒットさせることはできませんが、その情報をOCRでテキスト化すれば、検索で利用することが可能になります。われわれは、普段、PCやスマートフォンで何かを調べる際には、検索ボックスに、調べたい言葉を入力しますが、その際ヒットされる情報はすべてテキスト情報です。テキスト化されているからこそ、求めている情報を取り出すことができるのです。逆に言うと、テキスト化されていない情報を探し出すことはきわめて難しいということです。ということは、情報が容易に利用されるためにはテキスト化は欠かせないということが言えます。
しかし、歴史情報を扱う組織が所蔵するデジタル化された資料の多くは、紙資料のデジタルデータです。それは、現在デジタル化された資料となっていたとしても、あくまでも、画像データにすぎません。紙がデジタル撮影されただけなのです。よって、その画像にある文字情報はテキスト化されていません。そのような画像データにある文字は、ボーン・デジタルの文字(作成当初からテキストとなっている文字。Wordなどで作成した文字)ではないのです。
しかも、そのようなテキスト化されていない地域情報は膨大にあるのです。たとえば、沖縄県公文書館では、現在、琉球政府文書のデジタル画像(テキスト化されていない画像)の公開を進めていますが、その量は十数万簿冊もあります。また、南城市(4町村が合併して誕生)にも、旧4町村の広報(テキスト化されていないPDF)が約1万頁あります。これらの画像文字情報が、テキスト化されて、検索できるようになれば、研究の効率性は各段に向上するでしょう。それゆえに、OCRによるテキスト化の意義は大きいと言えるのです。
3つ目のネットワーク化についてですが、このネットワークは、入江氏の述べているスケールで考えた場合、国と国をまたがるネットワークです。国境を超えて、複数の国が協力して構築するデジタルアーカイブが理想的なものであると、筆者は考えます。それが実現できている有名なデジタルアーカイブは、Europeanaです。このウェブサイトのHP(2023年8月16日閲覧)をみると、こう書かれています。
Discover Europe’s digital cultural heritage
Search, save and share art, books, films and music from thousands of cultural institutions
(訳)
ヨーロッパのデジタル文化遺産を発見しよう。
数千の文化施設にあるアートやフィルム、音楽を、検索し、保存し、そして(ほかの人と)シェアしよう。
ここに「thousands of cultural institutions」とある通り、Europeanaでは、ヨーロッパの数千の文化施設のデジタル資料を調べることができます。「cultural」とありますが、実際には、歴史素材もたくさんあるので、Europeanaは歴史文化デジタルコンテンツを大量に公開していると言ってよいと思います。
なお、所蔵点数も膨大です。HPにある検索ボックスには、「Search 50+million items」と書かれています。つまり、検索の対象となる資料が5千万点以上もあるということです。
ヨーロッパの国々は共通の歴史を持つとはいえ、敵対しあった歴史もたくさん持っています。にもかかわらず、現在、国境を超えてデジタルアーカイブでネットワークを形成することができているというのは、素晴らしいことです。まさに、Europeanaは、入江氏のイメージする「記憶の共同体」を具現化する歴史文化プラットフォームです。
Europeanaと同じ様な歴史文化デジタルコンテンツのプラットフォームが、アジアにもあったほうがよいと、筆者は考えます。いきなりアジアのすべての国々と、共通のデジタルアーカイブをつくるというのは難しいかもしれませんが、せめて、つながりの深い東アジアの国々で、共通のデジタルアーカイブをつくるべきだと、筆者は思います。そして、市町村単位の地域も、その広域ネットワークのアーカイブに加わることができるようになることが理想的です。そうなると、地域情報は、閉じられた空間の中のレアなローカル情報ではなく、開かれた空間の「人類の共有財産」となるのです。
以上、情報が広く利用されるようになるための方法を3つ提示しましたが、実は、これら3つのことは、公的情報サービスの従事者の間では、よく会話で出てくることで、珍しいアイデアではありません。
1つ目(多言語化)と2つ目(テキスト化)は、技術の進歩により、大きく道が開かれていくと、筆者は予想しています。問題は3つ目(ネットワーク化)です。現状を見ると、アジアで、Europeanaのようなプラットフォームをつくるようになることは想像できません。その理由は、歴史に対する考え方の違いであると、筆者は考えています。入江氏によると、ヨーロッパでは、負の歴史も共有財産として考えられています。どの国の人間もその財産を使って学べばよいという、ある意味、割り切った考え方があるというわけです。一方、アジア諸国では、歴史認識や解釈で、いまだに、いがみあっています。「ポジティブな歴史も、ネガティブな歴史も、同じ場所に並べて、みんなで多元的に見てみよう」という空気が希薄なのです。この点を打破することが、日本のデジタルアーカイブにおける大きな課題であると、筆者は考えます。
次章では、ネガティブな情報に接する重要性について述べます。
多様性を高めるには、多種多様な情報に触れることが大事ですが、「多種多様な情報」の中でも、本章では特に「ネガティブな情報」について述べます。ポジティブな情報だけでなく、ネガティブな情報も必要であることを、主に哲学者ガダマーの研究を援用しながら、説明します。また、そのこととデジタルアーカイブとの関係についても触れます。
(1)デジタルアーカイブの責任
これまで、主に次のことを述べました。
・地域の歴史文化情報は、世界の共有財産である。
・すべての人々は、「共通財産」を用いて、共有しうる歴史を学んでいくことにより、グローバルな結びつきを一層密接なものとすることができる。
・デジタルアーカイブで多種多様な地域情報を、大量に公開するべきである。
・多言語化、テキスト化、ネットワーク化により、地域情報が利用されやすくすることが望ましい。
地域情報を世界の共有財産ととらえて、積極的にインターネットという拡散性の高いツールを使って公開していくことは、たしかに理想的です。しかし、多くの情報を多くの人の目に触れるようにするということは、大きい社会的影響力を持つということなので、それだけの責任が伴います。
また、多種多様な情報を大量に公開し、しかも、利用されやすくするためにテキスト化や多言語化、ネットワーク化をするとなると、業務量が増えるので、その分、過失を犯す可能性も高まります。ミスを起こさない責任というものも大きくなります。
そのように責任が大きくなると、実務担当者は気後れするようになります。しかし、筆者は、そこで尻込みしてはいけないと考えています。たしかに、仕事の量が増えればそれだけリスクも増えます。たとえば、①誤った解説をつけて、市民から指摘されて恥をかく、②プライバシー性が低いと判断して公開した資料であるにもかかわらず、「プライバシーの侵害」と指摘されてしまう、③理不尽ないいがかりをつけられてしまう、など、予期せぬ事態が起こる可能性が高まります。
しかしながら、それらを単にリスクとみなすのではなく、「業務を改善していくための良い機会」ととらえることが重要であると筆者は考えます。そう思って、アクセルを踏まないと、多様性の高いデジタルアーカイブを構築することはできません。公的情報サービスの従事者は、まずは、情報の多様性を高める社会的責任を一番の責任と考えて、そのために尽力するべきです。正確な情報を出すということと、人権侵害を避けるということに対して最善を尽くしているなら、いつも堂々としているべきです。その努力をしているにもかかわらず起きるトラブルは「仕方がないこと」です。そのトラブルを恐れていては、多種多様な情報を大量に公開することはできないでしょう。
とはいえ、闇雲に、なんでもなんでも情報を収集し公開することには、筆者は反対です。まず、重要な情報は何かを選ぶ基準を持つべきです(特集「なんじょうデジタルアーカイブで何を残すか?―写真資料の重要性―」の「3.どのように資料内容の価値判断をするのか?」を参照)。また、根拠の薄い、デマの類の情報や主張(例:ナチスのホロコーストはなかった)は、排除されるべきです。なお、神話や伝説、聞き伝えなど「事実とは言い難いが、文化的に重要な情報」を扱う場合には、史実でない可能性を記さねばならないです。それらのルールを守ることも、大きな責任の1つであると、筆者は考えます。
そして、世界に発信するという意味を考えるべきでしょう。インターネットで公開する限り、それを考える責任があると、筆者は思います。世界の「記憶の共同体」の一員として「世界標準のデジタルアーカイブ」を構築するのであれば、閉鎖的であってはいけません。お国自慢はご法度です。たんに多種多様な情報が大量に公開されているというだけでも十分ではありません。多様性の高さが強く求められます。先に「多様性を高めるためには、ネガティブな見方(批判的な見方)は絶対的に必要」と述べましたが、次項では、ポジティブな情報とネガティブな情報の両方を公開することが重要であるということを、哲学者ハンス・ゲオルク・ガダマーの言葉を援用しながら説明します。
(2)多様性を高めるためのネガティブ情報
1人の個人の中で、多様性を高めるためには、まず、固定概念(先入観、偏見、現時点で正しいと思い込んでいる考え)を、いったん宙ぶらりんにする(未解決の状態にする)必要があります。それについて、ガダマーは次のように説明します。
問うということは未解決の状態におく(ins Offene stellen)ということである。問われた事柄の未解決性は、答えが定まっていないというところにある。問われた事柄は確認され決定されるまでは、また宙に浮いているはずである。問われた事柄をその疑わしさについて未解決においておくことに、問いの意味がある。問われた事柄は宙ぶらんの状態におかれて、賛成論と反対論の釣り合いが保たれるようでなければならない。問いはどれも、このような宙ぶらりんの状態を経て、未解決の問いとなることにより、はじめてその意味を完成させる。
[ガダマー2008:562]
多様性を高めるためには、まず、未知の情報に触れることにより、現在の自分の考えが正しいのか正しくないのかを検証しなければなりません。検証することは「批判的に問うこと」ですが、批判する前に、現在の考えを「未解決の状態におく」必要があります。その状態は、賛成論と反対論が拮抗している状態(どちらが正しいか判断が難しくなっている状態)です。
このように、現在の考えを宙ぶらりんにして、自分の考えが誤っている可能性も認めながら、相手の考えに対して、否定的な考えを投げかけるという思考プロセスが、新たな考えを身につける(多様性を高める)ためには必要なのです。否定的な考えを投げかけるということは、開放的な姿勢を持ちながら問うということです。それについて、ガダマーはこう述べています。
経験の弁証法的否定性が、完成された経験という理想(完成された経験では、われわれは自らの有限性と限界の全体に気づいている)において完成するように、問いの論理的形式とそこにひそむ否定性は、ある根本的な否定性において完成する。その否定性とは無知の知である。難問のもつ最高の否定性によって問うことの真の優位性を明らかにしたのは、ソクラテスの<知ある無知 docta ignorantia>である。
[ガダマー2008:560]
ガダマーのいう「否定」とは、こういうことです。自分を批判的に見る。自分の無知を知る。自分の有限性を知る。完全な知識を得ることは不可能と認識する。だから、自分より優れているかもしれない他者の知恵を得るために、問いを立て続けなければならない。
この自己否定性こそが、ソクラテスの<知のある無知>のエッセンスです(<知のある無知>は、「無知の知」としてよく知られている)。そして、ガダマーは、「否定」を通じて新たな学びを得られると、次のように主張しています。
否定的な事例を通してこそ、新しい経験をえることができる。そのような経験も経験の名に値する限り、期待を破る。だから、人間という歴史的な存在の本質的局面には、根本的な否定(Negativität)があり、この否定性は経験と洞察の本質的なつながりにおいて明るみに出る。
[ガダマー2008:551]
新たな経験(学習)をするには、否定(ネガティブに見ること)が必要ということです。新たな情報により、自己も他者も否定的に眺め、新たな視点を獲得し、知的枠組みを広げ、判断能力を高めていく。これが、多様性を高めるプロセスであると、筆者は考えます。
「否定」についてもう少し詳しく説明します。2人の人間が討論をしているとします。または、本の著者と討論しているつもりで読書をしているとします。その際、ガダマーは、自分と意見の異なる相手の身になってみることが必要であると言います。
わが身を置き換えることは、ある個性が他の個性に感情移入することではないし、他人を自分の尺度に従属させることでもない。それはつねに、自分の個別性ばかりでなく、他のひとの個別性をも克服して、自分をより高次の普遍性へと高めることを意味する。
[ガダマー2008:477]
まず、相手の立場に立つことは、「感情移入」ではない、つまり、完全に相手の考えに飲み込まれてしまうことではないということが述べられています。次に、逆に、相手の考えを自分の考えに従属させてはならないということが述べられています。
要するに、両側の視点を持つことが必要ということです。「自分の個別性ばかりでなく、他のひとの個別性をも克服」するということは、「自分という特殊な歴史性をもつ存在」が、「他者という特殊な歴史性をもつ存在の立場」に立ち、自分の無知や閉塞性を知って、新たな知識や考え方を身につけ、視野を広げるということです。視野を広げるということは、より普遍的に考えることができるようになるということです。「自分をより高次の普遍性へと高める」というのは、そういうことです。なお、他者の意見を理解するということについて、ガダマーは、次のように述べています。
他者の意見を理解するとき、事柄に関する自身の先行意見に盲目的に固執することなどできない。もちろん、だれかの言うことに耳を傾けたり、読書したりする場合、内容に関する先行意見や自分自身の意見をすべて忘れなければならないというわけではない。求められているのは、ただ、他者やテクストの意見に対する開かれた態度だけである。しかし、このような開かれた態度は、他の意見を自分自身の意見全体に関連づけたり、逆に自分の意見をその意見にかかわらせたりすることを、いつもすでに含んでいる。
[ガダマー2008:426]
ここで述べられていることは大きく2つあります。1つは、他者に開かれた態度をとるということです。これは、自分は無知であるという前提に立ち、まずは他者の言葉に素直に耳を傾けてみるということです。もう1つは、他者の意見を自分の意見に関わらせるということです。これは、自己の無知の部分を補い、さらに、誤った部分を修正するという作業です。
筆者は、この1つ目がとても重要であると考えています。これは、競技としてのディベイトの思考法とは異なります。ディベイトでは、勝つことを目的とします。よって、「相手の意見を全否定し、自己の意見を全肯定する」という思考で、討議を行います。しかし、ガダマーの言う「否定に対する態度」は、「自己の考えをいったん判断停止状態にし、相手の立場に立って相手の知識や知恵を検証し、正しい批判を積極的に受け入れるという開かれた態度」です。まずは、自己の心を開放するのです。多様な世界を受け入れるということには、このような開放的な心の持ち方が必要なのです。
(3)デジタルアーカイブとネガティブな情報
ここまで、個人の多様性を高めるためには、「否定」が必要であるということを述べてきましたが、最後に、これに関連して、デジタルアーカイブのあり方について説明します。
なお、本稿でいうデジタルアーカイブとは、主に地方自治体が運営する公的なデジタルアーカイブを意味します想定しています。情報とは、同デジタルアーカイブが扱う地域情報のことです。
まずは、ある個人があるデジタルアーカイブを利用するときのことを考えてみます。その人が利用するデジタルアーカイブが、次のような点を満たしていたら、その利用者は多様性を高めることができると、筆者は考えます。
・1つのこと(テーマや出来事、人物、モノ)について、多くの情報がある。
・1つのこと(テーマや出来事、人物、モノ)について、対立する内容の情報がある(ポジティブな情報とネガティブな情報がある)。
この2点を満たすことは、実は、簡単ではありません。特に後者の点を満たすことは難しいです。たとえば、あるデジタルアーカイブの運営者が世間に郷土の魅力や誇りを発信しようとする際、その地域にとってネガティブな情報を積極的に収集して公開するとは思えないからです。たとえば、次のような情報を積極的に収集し、詳細な解説をつけて公開するとは考え難いです。
・郷土が誇る人物の栄光の裏で、その人物のせいで残酷な仕打ちを受けた人もいた。
・郷土が誇る名所の観光整備事業で、過去に汚職があった。
・名所の説明板にある「郷土の一部の人にとって好ましくない歴史情報」が、識者や市民の反対を押し切って、削除されることになった。
・その「歴史的偉人」の有名な美談は、かなり誇張されているということが、最近の研究で明らかになってきている。
歴史を担当する情報サービスの従事者は、これらのネガティブな情報もポジティブな情報と併せて収集・公開するべきでしょう。そうしないと、大本営発表のようなサービスを行うことになります。
大本営発表のような偏った情報サービスはよくないということは、誰でも、頭では理解しています。しかし、実際に、「郷土の誇り」に関するネガティブな情報をその郷土で公開することには、大きな勇気が必要となります。「地域の情報は、ポジティブな情報であれ、ネガティブな情報であれ、ともに人類の共有財産であるから、等しく収集・公開されなければならない」と堂々と主張することは簡単ではありません。簡単でないからこそ、筆者は、あえて本稿で主張しています。多様性を高めるには、ガダマーのいう「否定」のプロセスが不可欠なので、そう主張せざるを得ないのです。
なお、歴史家・安良城盛昭氏も、地域史のあり方として、筆者と同様のことを次のように述べています。
いろんな意味で自分たちの祖先とか、自分たちの生きてきた歴史とか生活を反省していくということです。
[安良城1977:20]
反省するということは、批判的に過去を検証して、その結果を未来のために生かす、ということです。よって、反省は、より高い知に向かう、建設的な精神活動であり、ガダマーの「否定」と類似します。まず、情報サービスの従事者が、負の歴史にも向き合い、反省することが必要であると言えるでしょう。
もし、実務担当者が反省のプロセスを経ずに「郷土自慢に拘泥した情報」ばかりを公開すれば、利用者を視野狭窄に陥らせることになります。視野狭窄に陥れば、多様性を高めることができなくなります。それは社会リスクの1つです。デジタルアーカイブでの公開であれば、拡散性が高くなるので、その分、視野狭窄に陥る人の数も多くなります。これが、デジタルアーカイブの怖いところです。
ところが、多様性の担保された巨大な図書館では、そのような危険に陥ることはありません。そこでは、1つのテーマについて様々な主張をもつ書籍がたくさん同じ棚に並べられているからです。利用者は、そのような棚を見て、1つのテーマでもいろいろな考え方があることを知り、一方の主張だけを信じるのは危険であると感じます。ガダマーの説明で述べた通り、一種のパニックに陥り、いったん結論を保留し、問いを発するようになるのです。
この思考プロセスが、個人の多様化を高めます。逆に言うと、「否定」のない思考プロセスは、多様性を低くします。よって、偏った内容の情報だけを揃えているデジタルアーカイブは、一種の情報操作装置であると言えます。このようなデジタルアーカイブを構築することが、公的情報サービスの目指すべきことでしょうか。そうではないと筆者は思います。
では、かりに、多くのデジタルアーカイブが、ネガティブな情報も含めて様々な情報を網羅するようになったとしたら、それで十分でしょうか? 筆者はそう思いません。なぜなら、どれだけ高い理想を掲げて多様性を高めるための努力をしたとしても、個性を持つ人間が、デジタルアーカイブを管理運営する以上、発信する情報に多少なりとも偏りが生じることは避けられないからです。それらのアーカイブが、各々独立して存在している以上、偏りの補正をすることは難しいでしょう。たとえ、ある地方自治体のデジタルアーカイブ担当者たちが、偏りの補正を真摯に行ったとしても、それは、あくまでも内輪での作業にすぎないので、その補正成果は限定的となるでしょう。よって、ある利用者が、あるデジタルアーカイブだけを利用する場合、どうしても、そのアーカイブの色に染まることになるのです。
それならば、1人の利用者ができるだけ多くのデジタルアーカイブを利用すればよい、という意見がでてくるかもしれません。しかし、たとえ、1人の利用者が、複数のデジタルアーカイブを使ったとしても、その数は限定的にならざるをえないでしょう。なぜなら、2つの問題があるからです。1つ目は時間の問題です。もし、ある利用者が日本各地に存在する事柄について調査している場合、日本中のデジタルアーカイブの資料を渉猟する時間的余裕はないと思えます。2つ目は知識の問題です。ここでいう知識とは、「その利用者が研究対象とする情報がどのアーカイブで公開されているか」という知識です。そのような知識を完全に持っている人はいないでしょう。
この2つの問題を克服する方法は、ネットワーク化です。もし、世界中のデジタルアーカイブがネットワーク化されていて、1つのHPで、全デジタルアーカイブの資料を調べることができるようになれば、これらの2つの問題は解決され、その結果、利用者は1つのテーマをより多角的に考察できるようになります。そして、最終的に、より偏りの少ない研究ができるようになります。
ヨーロッパのEuropeanaは、このような理想をある程度実現できています。Europeanaは、数千のデジタルアーカイブとネットワーク化ができています。このようなプラットフォームを使えば、偏見から解放されやすくなります。しかし、筆者は、ヨーロッパ規模だけでなく、世界規模のネットワーク化を望みます。ある研究テーマが世界の様々な場所と関係している場合、ネットワーク化はとくに効果を発揮します。
では、どのような研究がそれに該当するでしょうか。筆者はここで集団自決を例に挙げたいと思います。集団自決と言えば、沖縄の集団自決が有名ですが、先の大戦では、沖縄以外の場所でも、集団自決は起きました。その1つは、サイパン島マッピ岬です。自決者の数は、千人とも千五百人ともいわれます[中日新聞社会部1995:232]。満州でも、関東軍が後退する中で、ソ連軍の進撃や中国人の襲撃が起き、開拓団員たちは集団自決を行ないました[太平洋戦争研究会編2005:224-226]。当時、多くの沖縄人がサイパンにも満州にもいたので、「先の大戦での沖縄人の集団自決」の調査のためには、それに関する資料が公開されているあらゆるデジタルアーカイブがネットワーク化されていることが望まれます。もし、デジタルアーカイブが世界の広域でネットワーク化されていて、なおかつ、多言語対応が実現できていれば、集団自決の調査のために、中国やサイパンのデジタルアーカイブの資料も同時に利用できるようになります。複数のデジタルアーカイブを「はしごする」必要がなくなります。しかも、強制的に多種多様な情報を大量に突きつけられることになるので、否応なしに、自分の知識の薄っぺらさや思考の短絡さに気づかされたり、好奇心を高めたりするようになります。これは、認知的複雑性を高めることにもつながります(その重要性については、「多様性とデジタルアーカイブ①」で述べています)。
また、世界規模のネットワーク化と多言語対応は、研究の幅を大きく広げます。そのことは、集団自決の研究の枠組みを「先の大戦」から「すべての時代」へと広げた場合を想像してみると、よくわかります。沖縄や満州、サイパンのケースに加えて、マサダの集団自殺やカルト宗教団体「人民寺院」の集団自殺なども学ぶことができるようになるでしょう。そのような学習が、1つのHPでできるというのは、画期的と言えます。
さらに、集団自決の多種多様な事例と解釈に触れることにより、「人間はどのような条件において集団自決を行うのか」という考察を深めることができるようになるでしょう。つまり、普遍的な英知により近づくことができるようになるのです。ガダマーの言う「自分をより高次の普遍性へと高める」とは、こういうことであると、筆者は考えています。
なお、そのような調査で触れる1つひとつの情報は、まさに「世界の共有財産」と言えるでしょう。入江昭氏は、一国中心の歴史研究ではなく、グローバルなつながりを強化するための歴史研究を推奨していますが、デジタルアーカイブは、そのような研究を促進する最高のツールと言えるでしょう。
ここで、これまで説明してきたことの要点をまとめておきます。
・世界のどこかで起きた出来事は、世界人類の共有財産として考えるべきである。
・世界の共有財産としての地域情報を、世界で広く利用できるようにするということは、それだけ責任も大きくなる。しかし、「できるかぎり多様性を高める工夫をする責任」がもっとも大きい責任と考えて、リスクを恐れず前向きに業務を行うべきである。
・多様性の高いデジタルアーカイブを構築するには、ネガティブな情報も含めるべきである。
・ネットワーク化により、一度に、多種多様な情報大量に入手することが可能になる。
・多言語化により、情報の利用機会を増やすことができる。
・テキスト化により、情報の利用機会を増やすことができる。
これらのポイントは、本稿で筆者が主張したい主なポイントです。次章では、ポジティブな情報とネガティブな情報を持つテーマの具体例を3つ紹介します。その3つのテーマについて、各々、ポジティブな情報とネガティブな情報を記します。また、その3つに解説をつけ、ポジティブな情報もしくはネガティブな情報の片一方だけを知る場合と、それらを同時に知る場合で、理解の深さが大きく変わるということを明らかにします。
筆者は、かつて、ある大学生から「郷土自慢の内容のアーカイブで何が悪いのか」と反論されたことがあります。「自分の郷土を愛し、故郷に誇りを持ち、地域の先人に感謝の気持ちを持つことで、健全な精神を養える。郷土愛のない人間は、根無し草と同じだ。根のしっかりしていない人間は、郷土のために役に立つ人間になろうとしない。個人主義的な人間になってしまう。それでは、社会はよくならない」と、その学生は理由を述べました。それに対して、筆者は、このように言いました。「郷土を1人の人間に置き換えて考えてみたらどうだろうか。ある人間が自分の優れた点だけを見て、他者からの批判を一切受け付けないで、自分の自慢ばかりをしているとしよう。さて、そのような自己愛の塊のような人は、社会で高く評価されるだろうか。自己批判や反省を行なえない人間が、他者に対して適切な助言ができるだろうか。そういう人が、健全な形で社会の建設に寄与できるだろうか。答えはすべてノーだと思う。そういう人は、郷土に何も利益をもたらさないだろうし、個人主義的人間として嫌われるだけだろう。1人の人間も、1つの地域も、批判を受けるプロセスを経ることでのみ成長できるのであれば、やはり、アーカイブでも、ネガティブな情報を積極的に取りあげるべきではないだろうか。それに、ネガティブな情報こそが、反省のための宝の情報であり、人類の共有財産となりえる。自分は、ネガティブな情報には希望があると考えている」
その学生は、納得のいかない表情で「よくわからない」と言って去っていきました。それ以来、筆者は、ネガティブな情報の必要性について書きまとめたいと考えるようになりました。そして、ポジティブな情報とネガティブな情報の両方が揃っている「議論になりやすいテーマ」を探すようになりました。数年間探すと、思っていたよりも多く、そのようなテーマを見つけることができましたが、本稿では、それらの中から特に沖縄に関係するテーマを3つだけ選んで紹介します。
(1)尚巴志
まずは、第一尚氏王統二代の王(生没 1372 ~1439 年。在位 1422 ~1439 年)の尚巴志を取りあげます。
【ポジティブ】
・『中山世譜』などの正史によると、尚巴志が中山で実権を握った過程が次のように書かれている。察度のあと中山王となった武寧は悪逆非道の治世を敷き政治を乱した。これを遺憾とした佐敷按司尚巴志は、武寧に政道を改めるべきであると強く迫った。しかし、武寧は耳をかさず尚巴志を討つために諸按司に号令をかけた。しかし、按司たちは兵を動かさなかった。武寧は孤立し、降伏し城を出ていった。これにより、察度王統は滅亡した[伊芸2022:449]。
・正史『中山世譜』に、次の通り、尚巴志の徳の高さを示すエピソードが記されている。「異国商船有リテ、鉄塊ヲ装載シ、与那原ニ有リテ貿易ス。(中略)巴志、鉄許多ヲ得、百姓ニ散給シテ農器ヲ造ラシム。百姓感服ス」[福田2013:36]。つまり、尚巴志が異国船から鉄を手に入れ、それで農具を作って、百姓に分け与えたということである。
【ネガティブ】
・『中山世譜』などの正史に記された尚巴志に関する記述(武寧から尚巴志に実権が移った過程)は、歴史家の高良倉吉氏によると、易姓革命流の真実にもとる道徳的歴史叙述である。「真相は、正史のいうのとは正反対に、尚巴志による中山王位の簒奪とみるべき」[高良2012:84-85]と、高良氏は正史の記述に疑義を唱えている。正史では、舜天・英祖・察度の各王も、尚巴志同様、易姓革命の考えに基づき、道徳的に正しい道を辿って王になったということになっていて、その記述には政治的意図が見える。易姓革命とは、「中国に古くからあった政治思想といわれ、天子は天命により天子となり、もし天子に徳がなければ天命は他の人に下るという考え方である」[高良2012:51]。
・『中山世譜』には、次のような察度にまつわる話が記されている。かつて、金宮の前には牧港があり、日本からの商船が、多くの鉄塊を運んできていた。察度はことごとくそれらを買収し、多くの農具を作って耕作者に与えたので、農民から大いに慕われた。それによって察度は、浦添按司に推された。また西威王は王位に就く「仁人」ではなかったので、察度が推戴により即位した[福田2013:34]。異国船から鉄を買い、それで農具をつくって農民に分け与えたという点において、この察度の話は、尚巴志の話と同じである。これらの話のどちらも、徳のある人物が王になるという易姓革命の考え方に基づき創作されたと考えることが可能である。
【解説】
ネガティブな視点を持つことにより、次のことを知ることができます。
・正史にある記述のすべてを鵜呑みにすることはできない。史実に基づかないで創作された記述が含まれている。創作の目的は、時の為政者の権威を高めることであると推測できる。
・「鉄でつくられた農具」が正史に繰り返し登場するということは、それを用いることにより大きく生産性を上げることができたということを意味している。
また、次のように、さらに研究を深めることができます。
・正史では、古くからある定型モチーフが繰り返し用いられることがある。鉄の農具を農民に分け与えるモチーフ以外にも、様々なモチーフがある。例えば、日光感精型の説話が『中山世譜』で用いられている。英祖王の母は、日輪が懐に入って来るのを夢見て懐妊したと記されている。つまり、英祖王は、太陽神と人間の女の間に生まれたとされている。このような日光感精説話は、国内外で広く分布している[谷川2002:118-119]。また、正史の『中山世鑑』によると、察度の母は天女で、浦添間切謝名村の奥間大親と結ばれて、察度を生んだ後、羽衣を見つけて天に帰った、とある。このような羽衣伝説は、極東全体に伝わる異界交通神話に属し、日本では青森から沖縄まで流布している[伊芸2022:454]。このように、正史には科学的に説明のできない荒唐無稽な話が含まれているので、正史は「為政者にとって都合のよい歴史」であって「事実に忠実な記録書」ではないということがわかる。
(2)海洋博
次は、1975年に開催された海洋博のポジティブ・ネガティブの両面を紹介します。
【ポジティブ】
・海洋博の経済的効果は、公共・民間投資で3000億円以上、県民所得への寄与は1973年度7%、1974年度10%、1975年度8%と推計されている[琉球新報社編集局1992:43]。
・「中長期的に見た場合、海洋博はその後の観光業の成長に決定的な役割を果たす。観光業の拡大には飛行機などの旅客機、ホテルなどの客室数、バス・タクシー・レンタカーなどの移動手段といった受け入れ態勢の基盤整備が不可欠である。海洋博に向けた投資ブームは、短期間でそれを解決したのである。実際、72年に約44.4万人であった沖縄県への入域観光客数は海洋博が行われた75年に約156万人まで爆発的に増加し、その後、一時的な減少はあったが、さらに増加を続けていくことになる」[桜澤2015:186]。
【ネガティブ】
・「海洋博によって雨のように銭を降らせ、物価は日に日に上昇し、海洋博目当ての投機的な土地の買い占めはどんどん行なわれる。そしてこれは地価の高騰をまねき、若者たちのマイホームの夢を消しさり、農地は売却されて縮小され、賃金上昇による生産コストの上昇は農業を崩壊の危機に追いこみ、さらに若者たちは農業をすてて村から離れ、自然は乱開発されるなど海洋博のデメリットは大きい。とくに北部の自然はこの大型工事によって、すっかり様相を変え、山の緑は失われ、青い海は赤土で真っ赤に汚れ(後略)」[兼島1974:127]。
・「本部、名護、今帰仁に、伊平屋など北部の町村で本土企業や海洋博敷地に売り渡された土地は全体で200万坪といわれ、落ちた金がざっと100億円はこすといわれる。この土地ブームの売上金の配分で親子・兄弟が対立し、これまで平和だった農村に波風が立っている。そしてこれが原因で親子が離別したり、兄弟や親類が利害をめぐって争い、口もきかなくなったという例が多く、またトバクでスッカラカンになった人も少なくないという」[兼島1974:135-136]。
・「海洋博終了とともに企業倒産、失業者増など海洋博景気の反動がさまざまな形で噴出した。海洋博をあて込んでホテルや民宿、レストランなどが本部町に続々と建設されたが、それらのほとんどが目算がはずれた。観光客は、那覇と会場の素通り観光に終始。海洋博開催期間中から経営不振にあえぐところが多かった。農地を売り払い、農協資金などを利用して旅館などを建設したものの借金を抱え、夜逃げや自殺したケースも出た」[琉球新報社編集局1992:43]。
【解説】
これらを見ると、海洋博のもたらしたメリットもデメリットも規模が大きかったと言えます。メリットはわかりやすいです。経済的メリットです。観光を県の一大産業に押し上げるきっかけとなったことは、大きなメリットと言えるでしょう。
一方、デメリットは様々で、①環境破壊、②好景気の反動による不況、③農業の衰退とそれによる若年層の流出、④近親者との人間関係の崩壊などがあると言えます。ネガティブな視点を持つことは有益です。なぜなら、巨大な開発を行う際に、これらのデメリットの発生を最小限に抑える方法を考えることができるようになるからです。
なお、この海洋博の問題と似た、自然破壊を伴う環境問題は、世界各地で起きています。環境問題は自然破壊以外の被害も多々生み出す、複雑かつ深刻な問題であり、世界全体で研究するに値します。環境問題は、入江昭氏がいう「一国中心の歴史ではなく、すべての人々が共有しうる歴史」の典型的な例と言えるでしょう。
ここで、海洋博の問題と似た海外の例を1つ挙げます。経済学者の宮本憲一氏は、カナダのオンタリオ地方のインディアン居留地に入り、パルプ工場の廃液による水俣病の状況を調査しましたが、そこでわかったことは、インディアンが狩猟と観光ガイドという仕事を失い、さらに魚をとることを禁じられたため、ノイローゼになったり、アルコールに浸るようになったり、自殺するようになったりしたということでした。また、殺人・放火事件も続出しました[宮本1992:7-10]。
突然の大きな環境変化は、外的問題だけでなく、人間の心の問題も引き起こすという点では、このカナダの問題と海洋博の問題は共通しています。その他の環境問題でも、同様の事態が起きている可能性があります。ということは、海洋博におけるネガティブな情報は、世界に向かって発信するに値する研究材料、つまり世界の共有財産であるということが言えます。
なお、宮本氏は、環境問題の研究のあり方について、次のように述べています。
環境問題の全体像をあきらかにしようと思えば、医学だけでなく、工学や理学、さらに社会科学との連携が必要になります。もし、個別科学がみずからの分野に固執すれば、環境問題は学際的で総合的な領域にあるので、永久に解決できないのです。ところが、現代の科学の弱点は総合性がとぼしく、学際的研究の研究が少ないということです。
[宮本1992:10]
宮本氏の主張する通り、問題を学際的にみることは現実に即しています。これは、多様性の高いアプローチとも言えます。
(3)牛島満
沖縄戦で第32軍を率いた牛島満軍司令官は、沖縄戦に関する書籍で必ずといってよいほど、批判的に書かれています。それには、それなりの根拠があります。
また、一般論として、戦争で責任のある地位にあった人間の言動を批判的に考察することは、学術の発展のためにも、社会正義の構築のためにも、徹底的に行わねばならないことです。
しかし、ただ批判するだけでよいかと言うと、筆者はそうではないと思います。なぜなら、筆者は、歴史を多面的に見ることが、多様性を高めるために必要であると考えるからです。実際、人間とは単純な生き物ではありません。「完全な善人」もしくは「完全な悪人」と2種類にすっきり分けられるわけではありません。戦争で舵取りを誤った人間が、全員、生まれつき悪魔のような人間で、生涯を通して悪魔のように生きた、と言えるかというと、そうは言えないのです。かれらにも、常識的な側面や人格的に優れた部分があったと想像できます。
となると、「では、なぜ、かれらが、冷血で理不尽な舵取りをするようになったのか」という問いが生まれます。筆者は、その問題意識を持って、戦時の指導者たちを多面的に見ることが必要であると考えます。そうしないと、「戦時の社会システムが、かれらにどのように影響を与えたのか」を知ることができないからです。当時の社会システムを解明することは、歴史研究のもっとも重要な役割です。なぜなら、その解明ができれば、社会全体が同じ失敗を繰り返さないための手段を講じることができるようになるからです。
社会システムの解明のためには、「普通の人間でも鬼になりえる。では、鬼になる社会的条件は何なのか」と考えることが必要です。また、鬼になるプロセスを知るためには、鬼の状態だけでなく、普通の人間の状態も把握しなければならないことは自明です。
ここでは、牛島満を例に、彼のポジティブ・ネガティブの両面をみてみることにします。ここまでは、ネガティブな視点を持つことを強調してきましたが、ネガティブな情報が多くを占める場合には、逆の方向から考察することが必要です。ただたんにネガティブな視点だけを持てばよいと、筆者は主張していません。ネガティブな情報さえ集めていれば、多様性を高めることができるということではないのです。そのように誤解されないために、ここではあえて、ポジティブな面にも光を当てます。重要なことは、一方に偏ってはいけないということです。ガダマーの考えに基づき、相反する意見を持つ者同士が、いったん結論を宙づりにして、意見を交換することにより、議論をより高い次元に導くことができるということを思い出しましょう。
【ポジティブ】
・第32軍司令部壕では、「重要な首脳会議以外は個室にいて、ときたま訪れる若い参謀連中が持ってくる決裁書類に目を通しながら、わが子を諭すように何か教示している以外は、静かに読書にふけっている日常であった」[濱川1990:89]。摩文仁の軍司令部壕で、書き物と読書に余念がなかった[濱川1990:170]。
この証言はポジティブな側面を示す情報とまでは言い難いかもしれませんが、この証言から、第32軍のトップらしい荒々しさや剛毅さをうかがい知ることはできません。物静かな人物を想像させます。多くの犠牲を強いる指揮をした人物とは思えません。そのことは、第32軍参謀長・長勇のエピソードと比べると、より鮮明にわかります。長勇参謀長は、牛島司令官とは違って、次の通り、破天荒な面を持っていました。「参謀長の部屋では終日、賑わいを見せていた。ウイスキー瓶を片時も手放さない参謀長を取り巻いて、いろんな人々の出入りが激しく、時には女を入れてみるに耐えない痴態を繰り広げることもあった」[濱川1990:89]。摩文仁の軍司令部壕の参謀長室では、アルコールの臭いがただよい、豪快な笑いが絶えなかった[濱川1990:170]。
・首里の軍司令部壕から出て南下する途中、崎山町を過ぎたあたりからは、各所に将兵がうつぶせになって倒れているのが目につくようになってきた。その中には、あどけない顔の少年兵も見えた。牛島軍司令官は、これらを目撃するごとに立ち止まって黙禱を捧げた[濱川1990:134]。
・石川元常氏は、首里から南風原、知念村、玉城村を経て、現在のひめゆりの塔、健児の塔の近くの海岸で捕虜になった。石川氏は、捕虜になる前、空襲を避けるために、ある壕に逃げ込んだが、その壕の入り口にいた日本兵から「お前達が来る場所ではない。すぐ出て行け」と言われた。しかし、壕の奥から「敵機が去ってからにしなさい」と声がかかった。その声の主は、日本刀を肩にかけて椅子に座る牛島中将であった[琉球政府立那覇高等学校六期生(昭和28年卒)戦争体験記発行委員会2011:146-147]。
・字屋嘉部区出身の比嘉初子さん(当時21歳)は、ある日、前川大道の長毛小(現在の瑞慶覧長吉宅の東隣)でお茶の接待をすることになった。そこには牛島中将もいた。彼は、比嘉さんに幾つか質問をし、彼女の夫が海軍に出征し、2歳の娘がいるということを知ると、「女、子供は危ない、非戦闘員は疎開しなさい」と言った。比嘉さんが「今(2月の下旬)となっては疎開は自由には出来ません」と言うと、牛島中将は「私が証明書を書くからこれを持って行きなさい」とポケットから手帳を取り出し「非戦闘員は疎開を命ず」と書いた紙切れを渡した。その紙切れが証明書となり、鹿児島港行きの船に乗ることが許され、沖縄戦の戦火から逃れることができた[玉城村史編集委員会2004:642-644]。
【ネガティブ】
・1937年11月の南京包囲戦では、第36旅団長(熊本の第6師団所属)として参加し、追撃戦を指導した[藤原1987:83]。
・第32軍司令官牛島満は1944年8月31日、兵団長会同を開き次の訓示を出した。「敵愾心ヲ湧起シテ常在戦場ノ矜持ノ下作戦準備ニ邁進シ以テ必勝ノ信念ヲ固メ敵ノ来攻ニ方リテハ戦闘惨烈ノ極所ニ至ルトモ最後ノ一兵ニ至ル迄敢闘精神ヲ堅持シ泰然トシテ敵ノ撃滅ニ任セサルヘカラス」[榊原1983:175]、「極力資材ノ節用増産貯蓄等ニ努メルト共ニ創意工夫ヲ加ヘテ現地物資ヲ活用シ一木一草ト雖モ之ヲ戦力化スヘシ」[榊原1983:176]、「防諜ニ厳ニ注意スヘシ」[榊原1983:176]。
・第32軍司令部が1945年4月9日に出した命令書「球軍会報」の第5項には「爾今軍人軍属ヲ問ハズ標準語以外ノ使用ヲ禁ズ。沖縄語ヲ以テ談話シアル者ハ間諜トミナシ処分ス」とある[榊原1983:177]。
・軍の主力は消耗してしまっていたにもかかわらず、牛島司令官は、5月22日、「なお残存する兵力は足腰の立つ島民とをもって、最後の一人まで、そして沖縄の島の南の涯、尺寸の土地の存する限り、戦いを続ける」との覚悟から、南部への退却を決めた[読売新聞戦争責任検証委員会2006:135][吉田1996:36]。
・1945年6月18日、第32軍最後の文書による命令書を出し「鉄血勤皇隊をひきいて部隊の戦闘終了後はゲリラ戦にでよ」と一将校を、その指揮官に任命した[米国陸軍省1968:254]。
・1945年6月23日、「最後まで敢闘し、生きて虜囚の辱めを受くることなく、悠久の大義に生くべし」と最後の言葉を残して自決をした[石原1984:227]。
【解説】
ネガティブな点をまとめると、こうなります。①南京大虐殺に指導的立場で加担した。②捕虜になることを許さず、兵も民も含め、最後の一兵になるまで戦うことを命じた(全滅の可能性も視野に入れている点で異常である)。③命尽きるまで戦い続けることを命じておきながら、自らは自決した(卑怯である)。④方言の使用を禁じ、方言を話す者をスパイ(間諜)とみなした(アメリカ上陸前の1944年8月31日の段階では、閉じられた島の中で、島民がアメリカと接点を持ちスパイになる可能性は限りなくゼロであったにもかかわらず、「防諜ニ厳ニ注意スヘシ」と異常なまでに島民を疑った目で見ていた)。⑤南部への撤退を決めた(軍民入り混じる危険な状態での戦闘継続を決定)。
最後の⑤の決定が、どのような不幸な結果をもたらしたかについて説明します。牛島を司令官とする日本軍は、1945年4月24日、首里周辺の非戦闘員に、首里以南(沖縄本島南部)へ移動することを命じました。その時すでに北部への疎開が困難になってしまっていたので、住民は首里以南へなだれこみ、墓や自然壕などに避難することになりました。5月末頃から守備軍の南下が始まると、南部は軍民混在の状態になりました。その結果、住民は戦闘の邪魔になるという理由で、軍人が住民に被害を与えるということが起きました。例えば、①住民を避難壕から砲煙弾雨の中へ追い出す、②軍民雑居の壕内では、泣き声で敵に居場所が知られてしまうという理由で、日本兵が泣く赤子や幼児を毒殺したり絞殺したり軍刀により刺殺したりする、などの悲劇が数多く起きました。また、②と同様の理由で、日本兵に殺されるよりはと、母親が自らの手で愛児を殺すということも起きました[石原1984:227]。首里が陥落することが予測できた時点で米軍に降伏していれば、これらの不幸が生じることはなかったでしょう。住民はもちろん、兵の死傷者数も減らすことができたでしょう。そう考えると、南部で持久戦を展開するという選択は、明らかに誤っていたと言えます。
沖縄での組織的戦闘が終結したのは6月後半ですが、首里以南に撤退を開始する5月後半には、すでに日本が敗北することは目に見えていました。1945年2月のヤルタ会談でソ連の対日参戦がすでに決定していました。また、5月7日にはドイツが降伏していました。南部での戦闘継続は、ただ死傷者を増やす不幸だけを生んだのです。その意味では、牛島中将の責任は大きいです。
このように、牛島中将は人命軽視の指揮を執ってきましたが、一方で、上で紹介したポジティブなエピソードの通り、住民を生かすために心を配っていました。また、亡くなった人に黙禱を捧げるなど、人間味のある姿を見せていました。ポジティブな情報とネガティブな情報を並べて見ると、頭が混乱します。これらは同じ人間に関する情報とは思えません。これは一体どういうことなのでしょうか。
1つ立てられる仮説は、どのような人格の者が軍司令官になっていても、牛島中将と同様の采配を振るったであろう、という仮説です。つまり、どのようなパーソナリティの人間でも、軍の大方針を守る義務(社会的抑圧)から逃れることはできなかったであろうという仮説です。実際、沖縄戦は本土防衛までの時間稼ぎのための戦であり、戦闘の長期化が期待されていました。大本営が天皇に上奏して1945年1月に決定した「帝国陸海軍作戦計画大綱」によると、沖縄本島以南の南西諸島などは「皇土(=本土)防衛の為縦深作戦遂行上の前縁」とされ、そこに敵が上陸してきた時は「極力敵の出血消耗を図り且敵航空基盤造成を妨害す」ることになっていました[林2010:26-27]。軍司令官という立場を考えると、牛島は同大綱に基づいて行動するしかなかった、と言えるかもしれません。
そのほか、軍司令官という立場以前に、軍人という立場を考慮に入れる必要があるかもしれません。軍人の第一の任務はあくまでも戦闘です。沖縄戦では、敵に少しでも多くの損害を与えることを第一に考えねばなりませんでした。住民保護は最優先課題ではなかったのです。
また、当時、軍国主義一色に染まっていた日本では、国体護持のために勇ましく戦うことがもっとも重要なことで、国民の命や財産は軽視されていました。実際、1945年、鈴木内閣は5月から6月にかけて翼賛壮年団、大政翼賛会などを解散し、それにかわるものとして国民義勇隊をつくり、すべての国民を軍隊的編成に組みこむことで国民の根こそぎ動員を徹底させようとしました。さらに義勇兵役法によって、15歳以上60歳までの男子、17歳以上40歳までの女子全員を義勇兵役としました[荒井1990:36]。そのような時代に、牛島司令官にせよ、長勇参謀長にせよ、住民の命と財産を優先的に考えることは難しかったと言えるかもしれません。
このように考えていくと、もっとも大きな責任のあった人間は、悪しき社会システムをつくったり、維持したり、拡大したり、悪用したりした人間であると言えます。そうであれば、次の研究の対象は、おのずとそのような人間になるでしょう。
筆者は、牛島中将のポジティブな面を知ることによって、「なぜ彼は、まるで二重人格者のような行動をとったのか」という問いを立てることができました。そして、そのおかげで、いろいろと学ぶことができました。
筆者は、相反する情報を並べてみると、いつもパニックに陥り、モヤモヤした不快な気分になり、その落ち着かない気分をすっきりさせたいと思うようになります。そして、その謎を解くために、学びます。これは、ほかの多くの人にとっても同じではないでしょうか。この「モヤモヤ」が学習の動機になりうるのであれば、やはり、「モヤモヤ」を生み出しやすくするために、多種多様な情報に触れやすくするサービスを行うことが、公的情報サービス機関の役割になると言えます。当然、多種多様な情報の中には、対立しあう双方の情報が多数あることが望ましいです。
本稿は、「多様性とデジタルアーカイブ①」(7月21日なんデジ「特集」で公開)の続編で、多様性を高めることを大きなテーマとし、次の2つを中心に述べてきました。
・地域情報を世界の共有財産とみなし、広く世界で利活用されるように、デジタルアーカイブを改善させていくべきである。
・お国自慢(郷土自慢)のデジタルアーカイブから脱却するために、ポジティブな情報だけでなく、ネガティブな情報も含む多様な情報を多く公開するべきである。
繰り返しになりますが、筆者は、後者を実践することは容易ではないと考えています。ネガティブな情報を積極的に公開するということがいかに大変であるかは、公的情報サービスの実務を経験したことのある人であれば誰でも想像できると思います。物理的な問題により挫折するわけではないのです。心理的な壁に直面するのです。つまり、様々な「まなざし」を意識してしまうのです。それらは、地域の一般住民・地域の実力者・中央(都道府県や国)の「まなざし」です。それらの「まなざし」を意識すると、不安を感じます。ネガティブな情報の公開により誰かの気分を害することにはならないだろうか、と気をもんでしまうのです。そして、過剰に気兼ねする結果、多くの情報を闇に葬るようになるのです。
しかし、それでよいのでしょうか。戦前、「まなざし」への気兼ねが重なった結果、どのような社会システムが生まれ、何が起きたでしょうか。それを思い返せば、過剰な気兼ねはできなくなるはずです。
ここで1つ見習いたい例を紹介します。
米国立スミソニアン航空宇宙博物館が、原爆投下後の広島と長崎の街を映した写真を新たに展示する計画をしていることがわかった。従来は国内世論への配慮から、原爆の被害をめぐる展示はしていなかった。2025年に展示を刷新するのを機に、爆撃を受けた側の視点の紹介に踏み込む予定という。
(2023年7月31日付「原爆投下後の写真、スミソニアン博物館が展示計画 世論反発の過去も」『朝日新聞』 2023年8月28日閲覧)
筆者は、スミソニアン博物館が多くの「まなざし」がある中でこのような方針をとったことを称賛します。自国の歴史の暗部に光を当てることには勇気と英知が必要です。この方針を「自虐的」と言って蔑む日本人は誰もいないでしょう。スミソニアン博物館は世界の人々が歴史を公平にジャッジできるような展示を目指している、と筆者は思いました。スミソニアン博物館は、自国にだけ目を向けているのではなく、世界にも目を向けているのです。そのことは、次の通り、かれらのビジョン(Our Vision)からも読み取ることができます。
the Smithsonian strives to provide Americans and the world with the tools and information they need to forge Our Shared Future.
https://www.si.edu/about/mission 2023年8月28日閲覧
筆者訳:スミソニアン協会は、我々の共通の未来を築くために、アメリカ人と世界(の人々)に、かれらが必要とするツールや情報を提供する努力をする。
利用者は、アメリカ人だけに限定されていません。目は世界に向けられています。実際、スミソニアン博物館は、そのビジョンに沿って、世界に向けてウェブサービスを行っています。スミソニアン博物館のデジタルアーカイブ(Smithsonian Open Access)では、2023年8月28日現在で、450万点ものデジタル化されたコレクションが公開されています。1つの館としては、これはすごい数です。しかし、これで終わったわけではありません。2020年2月25日付「スミソニアン・マガジン」(Smithsonian magazine)によると、スミソニアン博物館は、約1億5500万点のコレクションのデジタル化を目指し、それらを徐々に公開していく計画を立てているのです。
日本の地方自治体のデジタルアーカイブは、スミソニアン博物館やEuropeanaから学ぶところがあると、筆者は考えています。それは、世界の様々な利用者に向けて多種多様な情報を大量に公開するという開放性です。
この開放性は、利用者の開放性を育て、やがては利用者の認知的複雑性(複雑なものを複雑なまま認識できる能力)を向上させるようになります。認知的複雑性が向上すれば、判断能力は向上します。そして、判断能力の高い人間が増えると、世の中全体の判断能力が向上するようになります。これは、人類の進歩です。人類の進歩と言っては大袈裟かもしれませんが、「多様性を高めるデジタルアーカイブ」を構築することができれば、微力ながらでもそのために世界に貢献できるのです。しかも、インターネットというツールを使って情報サービスを行なえるので、世界規模で貢献できるのです。ネットワーク化やテキスト化、多言語化を進めれば、さらに、サービスのスケールを拡大することができます。可能性は無限大と言ってよいでしょう。
このような話をすると、「屁理屈をこねるな」とか「妄想しすぎだ」とか言われることもあります。琉球政府文書十数万簿冊をデジタル化して公開する事業を立ちあげようとしていた頃には、面と向かって「バカじゃないの」と言われたこともあります。それは8年ほど前の話です。
しかし、この8年ほどの間に、デジタルアーカイブのスケールはどんどん大きくなってきています。先のスミソニアン博物館の例もそうですが、日本でも2020年ジャパンサーチが開設されました。ジャパンサーチは、「我が国の幅広い分野のデジタルアーカイブと連携し、多様なコンテンツをまとめて検索・閲覧・活用できるプラットフォームです」とHPで記されている通り、全国規模のネットワーク化を軸に、知的資源の利活用を進めています。また、この数年間で、地方自治体のデジタルアーカイブでも、コンテンツは充実してきましたように思えます。
世界中のデジタルアーカイブの担当者は、筆者同様、あれこれと難癖をつけられながらも、様々な理屈を考えて、デジタルアーカイブの重要性を説き、事業を拡大させてきたのだろうと、筆者は想像します。デジタルアーカイブのような歴史関連事業は、架橋などの土木事業とは違って、目に見える効果をすぐに出せない事業なので、その重要性を説明することは簡単ではありません。それゆえに、事業の推進には苦労が伴います。筆者は、常に「なにかよい理屈はないか」と考え続けてきました。そのささやかな成果が、2回にわたって紹介した「多様性とデジタルアーカイブ」です。この2本の書き物が、デジタルアーカイブを推進する同志にとって少しでも役に立つことを、筆者は願っています。
荒井信一1990「日本降伏への道」『日本同時代史1 敗戦と占領』歴史学研究会編 青木書店pp.25-47
安良城盛昭1977「市町村史のあり方を考える―地域の文化運動として―」『地域の目』第2号 安里英子(編)那覇出版社
伊芸弘子著、南城市教育委員会文化課市史編さん係編2022『大里のちてーばなし』南城市教育委員会
石原昌家1984『証言・沖縄戦』青木書店
入江昭2014『歴史家が見る現代世界』講談社
ガダマー著、轡田収・巻田悦郎訳2008年『真理と方法』2法政大学出版会
兼島清1974『沖縄―開発の光と影―』大日本図書
榊原昭二1983『沖縄・八十四日の戦い』新潮社
桜澤誠2015『沖縄現代史』中央公論新社
太平洋戦争研究会編2005『満州帝国』河出書房新社
高良倉吉2012『琉球の時代』筑摩書房
谷川健一2002(1999)『日本の神々』岩波書店
玉城村史編集委員会編2004『玉城村史』6玉城村役場
中日新聞社会部編1995『烈日サイパン島』東京新聞出版局
濱川昌也1990『私の沖縄戦記』那覇出版社
林博史2010『沖縄戦が問うもの』大月書店
福田晃2013『沖縄の伝承遺産を拓く―口承神話の展開―』三弥井書店
藤原彰編著1987『沖縄戦―国土が戦場になったとき』青木書店
宮本憲一1992『環境と開発』岩波書店
吉田健正1996『沖縄戦 米兵は何を見たか』彩流社
読売新聞戦争責任検証委員会2006『検証戦争責任』2中央公論新社
琉球新報社編集局1992『現代沖縄事典』琉球新報社
琉球政府立那覇高等学校六期生(昭和28年卒)戦争体験記発行委員会2011『戦時下の学童たち』琉球政府立那覇高等学校六期生(昭和28年卒)戦争体験記発行委員会