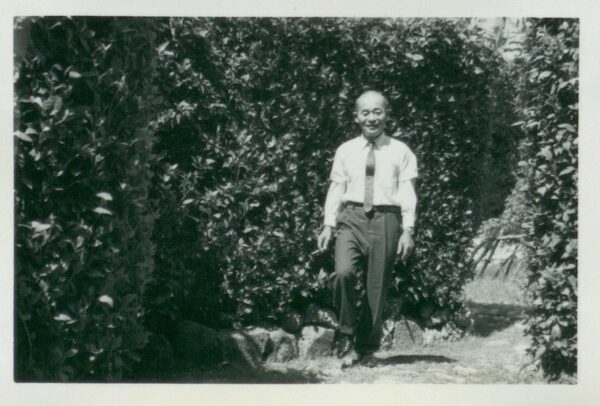
【資料群紹介】上原清光コレクション

南城市の戦争関係資料リンク集

湧上洋さんオーラルヒストリープロジェクト第4回目では、湧上さんの学生時代(小学生時代から大学生時代)のヒストリーを紹介します。湧上さんは、玉城国民学校、船越初等学校(現船越小学校)、玉城中学校、知念高校、琉球大学へと進学し、1957年に琉球大学文理学部化学科を卒業しました。戦中と戦後の復興初期における沖縄の学校教育は、現在と比べるととても十分と言えるものではありませんでした。沖縄戦の年(1945年)、玉城国民学校の4年生(10歳)だった湧上さんは、不遇な小中高校時代を過ごさねばなりませんでした。「落ち着いて勉強に打ち込めるようになったのは大学生になってから」と湧上さんは語っています。本稿では、湧上さんへのインタビュウで得た情報と文献資料を用いて、沖縄戦で焦土化した沖縄が復興していく中で、湧上さんがどのように学生時代を過ごしたのかを明らかにします。
湧上さんの小学生時代の教育は、現代の公教育と比較すると全く異なるものでした。戦時中(玉城国民学校時代)、「天皇のために命を捧げる」ことが美徳とされ、湧上さんは徹底した皇民化教育・軍国主義教育を受けました。沖縄戦の前には授業の代わりに陣地構築などに動員され、沖縄戦時には学校の授業はなくなりました。知念区の収容所に収容されるようになると、同収容所内に出来た学校で授業を受けることになりますが、教室も教科書もなく、その教育内容はとても十分なものではありませんでした。ここまでの出来事の詳細については、第2回目のオーラルヒストリーを参考にして下さい。
終戦後の1945年11月ころ、湧上さんは船越に戻り、船越初等学校に通うことになりました。同校時代のことについては、船越小学校『創立50周年記念誌』に掲載されている湧上さんの寄稿文に、次のように記されています。
船越小学校は、戦後、百名や志喜屋・知念等に収容されていた村民及び近隣村民と国頭方面からの住民が船越に収容されたことにより、児童教育の必要性から旧製糖工場敷地の現小学校用地に八年制の船越初等学校として設立されたのが始まりであります。
玉城村立船越小学校創立50周年事業期成会編 1997『創立50周年記念誌』p.135.
この通り、元々船越にいた住民以外の子供たちも、戦後、船越で学校教育を受けることになりました。船越初等学校の名称で戦後教育がスタートした時、湧上さんは5年生でした。この学校の教育も創立当初は、十分なものではありませんでした。それについて、湧上さんは同誌のなかでこう述べています。
最初は教室も教材もなく、青空の下で地面に座って木片で地面に字を書いて勉強したものです。しばらくして、戦争で破壊された製糖工場の建物や圧搾機、釜等が米軍部隊によって撤去され、整地されて、テント張りの教室が建てられ、更に一か月後にはカマボコ型のコンセット教室が建てられたと記憶しています。
玉城村立船越小学校創立50周年事業期成会編 1997『創立50周年記念誌』pp.135-136.
私たち五年生はテント教室があてられ、缶詰の木箱を机がわりに使用し、土間に座って私たちは授業を受けたものです。雨の日には、雨水がテントの中に流れ込み、授業ができなくなったことなどが思い出されます。
テント教室になってもノートの支給はなく、米軍の使用した英字の書かれた紙の裏面をノートがわりに使っていました。鉛筆の支給も少なかったので、短くなると竹筒にさして使ったものです。又、本もなく先生の本をべニア板で作った黒板に書き、それを書きうつして勉強したものです。
教材がなく、ノートと鉛筆が不足しているという状況で、まともな学習ができるわけがありません。このことだけをみても、現在がいかに恵まれているかがわかります。ノートの支給があったのはようやく6年生になってからです。しかし、その時でもまだ、生徒には教科書はありませんでした。先生だけが教科書を持っていましたが、それさえもガリ版刷りのものでした[玉城村立船越小学校創立50周年事業期成会1997:136]。
6年生の後、当時はまだ「6・3・3制」ではなく「8・4制」だったので、湧上さんは7年生となりました。その頃には、コンセット教室が出来、米軍の使用した折りたたみ式ベッドの骨組みに板を張って作った机が使われるようになりました。これでようやく机を使って授業を受けられるようになりましたが、椅子は自前で、家から缶詰箱や弾薬箱を学校に持って行かねばなりませんでした[玉城村立船越小学校創立50周年事業期成会1997:136]。
これらの湧上さんの回想をみると、つらい話ばかりですが、次のような楽しい思い出もあります。
終戦直後の五年生の時、米軍の野球場跡で学校と区民合同の大運動会が開催されたこと、週一回の農業実習ではじめて鍬をにぎって畑を耕し、イモを収穫して喜んだこと、七年生の時に八年生と一緒に選ばれて隣校リレーに出たこと(中略)などが想い出されます。特に、六年生の時の学芸会では、担任の玉寄兼三郎先生(愛地出身)が作った英語の会話のあるシナリオを私たち生徒に演じさせ、画期的なものとして大変な好評を博したことを今でも深く脳裏に残っています
玉城村立船越小学校創立50周年事業期成会編 1997『創立50周年記念誌』pp.136.
英語教育をまったく受けたことのない小学生が英語劇を演じるというのには驚きますが、「玉寄先生の指導力が卓越していたのでそれが実現できました」と湧上さんは回想しています。
なお、湧上さんの話によると、戦後直後、教員の資格を持つ先生はほとんどいませんでした。「鉄血勤皇隊」や「ひめゆり隊」などの学徒隊に所属していた人達が免許のないまま教員になっていました。湧上さんによると、かれらが生徒を引率して戦跡へ連れて行き、現地で起きた状況を説明するという校外授業がありました。これは平和学習のさきがけと言えるでしょう。
戦前と戦後では、教育の内容が大きく変わりました。筆者はその点について湧上さんが当時どのように感じていたかに興味を持ち、こう質問をしました。「戦前、先生達は、徹底した皇民化教育を生徒に押し付けました。にもかかわらず戦後は、民主主義を唱えました。そのような先生達に対して不信感や怒りのような感情を抱くことはありませんでしたか?」この筆者の問いに対して、湧上さんは「そういうことはなかったですね。戦後すぐは生活するだけで精一杯で、戦前の日本が悪かったと考えるだけの精神的な余裕はありませんでした。また、戦前、日本はすぐれているということしか言い聞かされていなかったので、その考えが終戦直後はまだ強く残っていたのかもしれません。ですから、教育の内容が戦後変わったからといってすぐに過去の教育に対して怒りの感情を抱くということはなかったのだと思います」と答えました。
湧上さんは、以上のような初等教育を受けた後、6.3.3制の施行に伴い7年生で修了となり、玉城中学校に2年生として編入することになりました。6.3.3制とは、1948年3月に学制改革要項により採用された初等学校(6年)・中等学校(3年)・高等学校(3年)の新学制です。6.3.3制では、初等学校と中等学校(初等学校および中等学校は、1952年に小学校および中学校に改称)は義務教育とされ、男女共学が全学校で実施されるようになりました[沖縄タイムス社1970:479]。
湧上さんは、玉城中学校に2年生として編入しましたが、その頃、玉城中学校は現在のグスクロード公園が所在する場所にありました。湧上さんは、そこで1年間学びましたが、翌年、同校は現在の場所(富里)に移転となりました。移転作業のために学校関係者は忙殺され、授業は十分に行われませんでした。
中学校での学習環境もよくありませんでした。入学当初教科書はありませんでした。そもそも教科書に限らず、書物というものを自分で手に入れることができませんでした。活字情報と言えば、先生が収集していた本だけでした。先生がそれらの本を参考にして黒板に文字を書き、生徒はそれを書き写していました。学校に図書室もありませんでした。本を選んで読むという今では当たり前にできることが当時はできなかったのです。小説が読めるようになったのは、高校に入ってからとのことです。また、「当時は、新聞を購読する人も見なかった」と湧上さんは回想しています。ようやく教科書で勉強できるようになったのは、中学3年生の頃といいます。


湧上さんは、中学校卒業後、知念高校に入学しますが、高校時代にも移転を経験することになりました。湧上さんが2年生の時に、親慶原から与那原への移転作業が行われました。知念高校の生徒は、校舎の解体や、解体資材の運搬など、様々な作業の手伝いをしなければなりませんでした。与那原では、校舎建築のために放課後に動員されました。当時の3年生は大学受験に集中しなければならないという理由で、その作業は免除されていました。そのため、2年生がその作業の中心にならざるをえませんでした。湧上さんは「2年生の時には勉強らしい勉強はできなかった」と回想しています。
知念高校は戦後、現在の与那原に落ち着くまで、移転を繰り返しました。同校の「2 学校沿革の概要」から移転に関する情報を抜きだしてみると次のようになります。
| 1945年11月16日 | 知念市志喜屋(現在の南城市知念字志喜屋)に創立、開校式 |
| 1945年12月7日 | 知念市百名(現在の南城市玉城字百名)に移転 |
| 1946年2月12日 | 大里村大見武(現在の与那原町字大見武)に分校設立 |
| 1946年4月1日 | 玉城村親慶原(現在の南城市玉城字親慶原)に移転(百名から) |
| 1946年5月10日 | 大見武分校が首里高等学校に合併される |
| 1952年2月17日 | 与那原町の現在地へ移転 |
このように校舎が転々と移動した時期と、湧上さんの学生時代が重なってしまったというわけです。
親慶原校舎時代の校長先生は、後に行政主席・知事となる屋良朝苗氏でした。湧上さんは「屋良さんはすばらしい校長先生でした」と言っています。数学担当の先生が時々病気で休むことがありましたが、その際、代理で、屋良朝苗校長が2クラスの生徒を講堂に集めて数学の授業を行いました。湧上さんは高校時代にそのような形で屋良校長直々の授業を数回受けました。「厳しかったですが、教え方はよかったです。とても理解しやすかったです」と湧上さんは回想しています。
屋良朝苗氏は自著『沖縄はだまっていられない』で知念高校校長時代のエピソードをいくつか記しています。ここでは、それらの中で、湧上さんの話と関連するものを紹介します。
学習環境が貧しかったということを湧上さんは繰り返し述べていますが、屋良朝苗氏はその点についてこう記しています。
知念高校在任中、昭和二十五年三月だったが、私は山城篤男氏(中略)真栄田義見氏らとともに、軍の方針によって祖国の教育指導者の講習(アイフェル講習)に派遣されることになり、軍用機で出発した。(中略)私たちは九州ブロックといっしょになり、九州大学で講習を受けた、講習は三か月間であった。私はこれまで本土の新教育というのは聞いてはいたが、実際にいって、新しい教育の実情をみてびっくりした。沖縄では図書を売る店さえなく、ましてや参考書さえわれわれはみたことがなかったが、福岡の街には参考書がみちあふれていた。
屋良朝苗1969『沖縄はだまっていられない』エール出版社、pp.147-148.
この一、二か年(知念高校に校長として赴任してからの一、二年)のあいだに私の胸を強くうったことは、生徒が教科書もノートももっていないことである。一度書いた紙をノートがわりに使っているみじめな姿をみて、これではたして高校の教育がなりたつものであるかと思ったものだ。
屋良朝苗1969『沖縄はだまっていられない』エール出版社、pp.138-139.
※括弧内は筆者追記
ここでも、湧上さんの話と同様に、本やノートが不足していたことが述べられています。次に、与那原への移転についてですが、これを決定したのは屋良朝苗氏でした。屋良氏は当時のことを回想して次のように記しています。
知念高校の敷地は、どちらかというと、民政府移転後は文化的中心からへんぴなところにかわっていたので、地理的にも文化的にも高校所在地としては適当でないと考え、私は与那原への移転を早急に決めるべきだと主張した。はじめは甲論乙ばくで、なかなか(受け)入れられなかったが、だんだん校区民の方も真剣に考えるようになって、これまで与那原移転に反対意見をもっていた人たちもわかるようになり、現在の知念高校敷地を決定した。この敷地の決定を置きみやげとして、実際移転までには手に及ばず、私は知念高校を去った。
屋良朝苗1969『沖縄はだまっていられない』エール出版社、pp.149-150.
ここで「民政府移転」と出てきますが、「民政府」(沖縄民政府)とは、米軍政府が沖縄諮詢会(米国軍政府からの諮問に対して答申する機関)を発展させてつくった民行政執行機関です。沖縄民政府は、司法と沖縄議会(知事の諮問に対して答申する機関)を有する政府で、沖縄人により運営されました。しかし、民政府とはいえ、実際には、米軍政府の命令や指示を実行させられる代行機関でした[沖縄タイムス社1971:170]。沖縄民政府の前身である沖縄中央政府は1946年4月22日に設立され、1946年12月以後に沖縄民政府になりました[宮里1966:3]。
「移転」とは沖縄民政府の那覇への移転という意味です。知念地区新里にあった沖縄民政府は、1949年7月に襲来したグロリア台風によって庁舎が破壊され、執務することが不可能になりました。そのため、那覇市の旧上之山小学校跡に移転することになりました。その後、新里周辺は、屋良氏曰く「文化的中心からへんぴなところにかわって」しまいました。高校の所在地として相応しくない土地であると判断されるようになったのです。このような背景があり、知念高校は与那原へ移転することになったのです。
知念高校には物象部というモノづくりを行う部活動組織がありました。湧上さんは1年生のときから物象部に所属していました。知念高校では毎年展示会が開催されていましたが、毎年、物象部員の作品が展示物の中心となっていました。
湧上さんにとって特に思い出深い出来事は、「都市模型」を制作したことです。これは1部屋ほどの広さがある大がかりな模型で、1人では作ることはできませんでした。湧上さんが1年生の時、3年生がこの展示物の制作の計画を立て、全学年の物象部員の手で制作することになりました。
この「都市模型」がどのようなものであったかは、『知念高等学校創立40周年記念誌』に掲載されている寄稿文(題:「科学創作展の思い出」)に詳しく書かれています。寄稿者の宜保盛信氏(元職員)は次のように記しています。
展示で最も人気を博したのは、物象部合作の都市模型であった。学年始めにたてられた綿密な計画にそって、必要な模型の制作分担がなされ、それぞれが作業にとり組んでいく。展示会の前日は部員総出で展示場の設営である。設計図にそって山や海、建物などが次々と仕上がる。バックの絵は安次富長昭君が腕を振るった。教室の周りを遮蔽して準備は終わった。それから夜を徹してのテストである。さて当日、満々と水を湛えた海、港には船が行き交い、電車はトンネルを出て鉄橋を渡り、またトンネルへ吸いこまれていく。山頂と街を結ぶケーブルカーは、ピストン運行だ。やがて周りが暗くなると街の家々には明かりがともり、ネオンが点滅する。燈台が淡い光を投げて廻る。その迫力たるや、模型であることを忘れさせる程であった。この創作展の評判は全琉に拡がり、遠く国頭からトラックでかけつける見学者もあった。
記念誌編集委員会1985『知念高等学校創立40周年記念誌』知念高等学校創立40周年記念事業期成会、pp.43-44.
このような手の凝った本格的なジオラマが高校生の手により制作されたことは驚嘆に値しますが、その分、かなりの時間が制作に費やされました。宜保盛信氏は、同寄稿文で「物象教室には発電機があり物象部員が交代で運転をしていたが、いつでも四、五名の部員が泊まりこみ、物象部の活動が途絶えることはなかった」[記念誌編集委員会1985:42-43]と述べています。筆者は高校生の泊まりこみが許されていたということに疑問を持ち、湧上さんにその点について聞きましたが「はい。4、5名が泊まり込んでいましたよ。授業を終えると一旦家に戻って夕食を食べ、また学校へ行くのです」という答えを得ました。筆者は怒る親がいたのではないだろうかと思い、それについても湧上さんに聞きましたが、「学校側に苦情を言う親はいませんでした。当時はおおらかだったのですね」という答えが返ってきました。
「バックの絵は安次富長昭君が腕を振るった」とありますが、安次富長昭氏とは、有名な画家で、知念高校物象部のOBです。2020年8月12日付の『琉球新報』では「1972年に琉大教授、国画会会員になった。沖展や国展の審査員も歴任した。06年には第42回琉球新報賞(文化・芸術功労)を受賞した。83年度沖縄タイムス芸術選賞大賞。10年瑞宝中綬章。16年度県功労者、那覇市政功労者。県工芸産業振興審議会会長、県文化財保護審議会委員などを歴任した」と紹介されています。湧上さんは、他2名と電車の制作を担当していましたが、電車の外観は、安次富長昭氏に描いてもらいました。
電車の制作で苦労したのは車輪作りでした。米軍の払い下げの旋盤を用いましたが、真円度の高い車輪をつくることは容易ではありませんでした。また、湧上さんは、電車の制作以外にも、電車のレールの制作も担当しました。これも高い精度が要求される作業でした。幅が正確でないと電車は走らないからです。
当時はあらゆるモノが不足していたので、材料や金槌などの小道具は、廃品の中から探しました。電車作りに用いたジュラルミンも、米軍の飛行場で廃棄処分されたものでした。目当てのモノがいくら探しても見つからない日もあったといいます。そのような徒労で終わる日があっても、とにかく「自力でなんとかする」という姿勢で部活動を行っていました。それは、学校の方針と一致していました。屋良朝苗校長も、「私が学校経営にとくに力を入れたことは、ないないづくしのなかで、それにまけず、創意と工夫をこらして自力で学校設備をととのえていくという、創造的、発展的学校経営を推しすすめていくことであった」[屋良1969:140]と述べています。









湧上さんは、特に大学へ行きたいと思っていたわけではありませんでした。しかし、親から大学進学を勧められたので、受験勉強をするようになりました。「これからの時代は、できたら大学まで行っておいたほうがよい。そのほうが良い仕事に就くことができるから」と親から言われたといいます。
受験勉強は決して楽なものではありませんでした。「受験勉強は大変でした。2年生の時には移転作業があったので、まともに勉強ができていなかったですから。それに、3年時でも夏休みは家の稲作の手伝いをしていました。田植えと収穫の時期には人手が足りず、どうしても手伝わねばなりませんでした」と湧上さんは言います。
湧上さんは、十分勉強に時間を割くことはできませんでしたが、無事、琉球大学へ入学することができました。船越出身で化学を教えていた先生の影響を受けて、文理学部化学科で化学の勉強をすることになりました。また、物象部の活動を通じて自然科学への関心が高まったということも、理系の道へ進んだ理由の1つでした。
湧上さんの大学時代で特筆すべきことは、兼島清博士との出会いです。湧上さんは、兼島博士から化学分析について多くのことを教わりました。兼島清博士は1922年沖縄生まれで、1943年台南高工卒業し、1962年東京工業大学で博士号を取得し、1963年琉球大学教授になりました。後には琉球大学理工学部長になりました。
筆者は、兼島博士の名前を聞き驚きました。なぜなら、湧上さんと会う前にすでに兼島博士の著書『沖縄―開発の光と影―』を読んで感銘を受けていたからです。そのこともあり、筆者は、兼島博士に関係する話を中心に湧上さんから話を聞きました。本章では、その聞き取り内容をインタビュウ形式で再現したいと思います。
――「『沖縄 開発の光と影』を読むと、人間としての温もりを感じます。自分自身が被害者であるかのごとく、公害被害に胸を痛めていることがわかります。たとえば、この本でこのような記述があります。「みんなが豊かな詩情と緑を愛する気持ちでより美しい街造りに努力すれば、必ず昔以上の立派な那覇市が生まれるだろうし、何としてもそうしたいものである」[兼島1974:34]とか「那覇市の河川の水質汚染を防止し、川を取りもどすことは、悪臭をなくし、環境を美化するだけのことではなく、われわれ自身を公害から守るためにも、急がなければならない問題である」[兼島1974:48]とかです。また、米海兵隊による実弾演習(1960年以降3回実施)が山野の火災をもたらしたことについてはこう記されています。「戦災によって焼野が原と化した沖縄の山野を、県民の緑化運動の努力によって、やっと緑がよみがえりつつあるときに、その努力をあざけるかのように、沖縄の美しい自然を、平和な今日でも演習という名のもとに焼きつくしている。このような米軍の暴挙に対し、県民は誰一人として強い憤りを感じないものはいない」[兼島1974:153]です。兼島先生は、大学でもこのような感じの人でしたか。
湧上
実際、その記述通りの先生でした。よい師匠に巡り合えたと思っています。先生のそのような考え方から影響を受けました。大学生の頃、先生に同行して調査を行うことも幾度かありました。地下に溜まっていたガスが上昇して外に出るということが当時よくありましたが、そのような時には、いっしょに現場へ行き、サンプリングし分析しました。建設工事中、深く掘るとガスが出ることがあったのです。那覇市内や知念などに同行した記憶があります。
――分析と言えば、この本では、1973年浦添牧港の米軍基地から排出されていた廃油が問題となり、「浦添市がサンプリングして、分析を依頼した」[兼島1974:146]と書かれていますが、依頼先は沖縄県でしょうか。この時代湧上さんは、沖縄県の職員になっていますが、当時のことで覚えていることはありますか。この本では、この問題について具体的に次のように記されています。「1973年5月浦添市牧港にある米軍基地から排出される廃油で沿岸海域が真っ黒に汚されていることに、浦添市が調査した結果、廃油の排出基準の614倍を超える量で、さらに重金属やPCBなどを排水から検出し、環境汚染が予想以上に大きなことが判明し、県民に大きなショックを与えた」[兼島1974:146]。何か思い出せることはあるでしょうか。
湧上
その分析に私自身が参加しています。分析は、浦添市から沖縄県に依頼されました。当時、県の公害衛生研究所(吉田所長)が中心になって分析を行っていましたが、この研究所では分析装置が、質的にも量的にも充実していませんでした。そのため、私の所属していた工業研究指導所が応援に入ったのです。私は、その浦添の件では、鉛の分析を担当したと記憶しています。
――調査分析のために、基地の現場に行ったのですか。
湧上
行きました。牧港の基地の中に、米軍兵でも入れない敷地があるのですが、その中に入って下水の水をサンプリングしました。もちろん、機密度の高い場所には案内されなかったですが。
――そのような分析技術は、大学時代に兼島先生から教わったことが基礎になっているのですか。
湧上
そうです。大学時代には、有機化学も無機化学も学びました。化学については広く学んだと思います。そのうえで、分析手法を兼島先生から教わったということです。
――大学で学んだ専門的な知識や技術を、就職先で活かすということを学生時代から考えていたのですか。
湧上
いいえ。将来学校の先生になるかもしれないと思い、教職免許を取る科目を履修していました(実際、教員免許は取得した)。大学時代には、その程度のことしか考えていませんでしたね。
――では、どのような経緯で、琉球政府に就職することになったのでしょうか。
湧上
実は、たまたま琉球政府で技官の募集があることを知ったのです。受けてみたら、採用されました。それだけのことです。しかも、面接だけの任用採用でした。当時は、化学を専攻している人が少なかったので、専攻採用の門は広かったのです。ですので、就職活動で苦労した経験はないですね。
――兼島先生の推薦状などは必要なかったのですか。
湧上
必要なかったです。本当に、面接だけで決まったのです。
――卒業後、兼島先生と何か接点はありましたか。
湧上
ありました。1969年と1970年の尖閣諸島の調査に一緒に参加しました。水質の調査をやりました。




湧上さんは、大学時代を除き、十分な学校教育を受けることができませんでした。小学時代には戦争があり、中学・高校時代には校舎の移転がありました。また、戦後の小中学校時代には、書物(教科書含む)やノートが不足していたので、勉強したくてもそうすることは困難でした。しかも、田植えと収穫の農繁期には家の農業の手伝いをしなければなりませんでした。あらゆる面で、現在の状況とは異なっていました。現在では、学校には図書室があり、地域には公共図書館があります。書店もあります。また、インターネットを利用すれば、近所の図書館にない書物を購入することができるだけでなく、世界中で発信されている様々な情報に接することもできます。学校の勉強で飽き足らない人は、学習塾に通うこともできます。それに、教科書以外にも、優れた参考書はたくさんあります。勉強したい人にとっては、今は最高の環境にあると言えるでしょう。
筆者が湧上さんとの話の中で、もっとも強い印象を受けたのは、高校時代の部活動です。物資が不足していた中でも、創意と工夫により巨大かつ精巧な「都市模型」を制作したという経験は、その後の人生に大きく影響を与えているのではないかと筆者は考えています。なぜなら、湧上さんは、琉球政府・沖縄県職員時代に様々な仕事に従事しましたが、どの仕事でも目覚ましい実績を残しているからです。また、定年退職後の活動においても、そのことは言えます。これらの詳細については、第5回目以降のオーラルヒストリーで紹介していきます。
文責:堀川輝之
沖縄タイムス社編・発行1970『1970沖縄年鑑戦後25年総合版』.
沖縄タイムス社編・発行1971『沖縄の証言:激動25年誌(上巻)』.
兼島清1974『沖縄―開発の光と影―』(環境科学ライブラリー9)大日本図書.
記念誌編集委員会1985『知念高等学校創立40周年記念誌』知念高等学校創立40周年記念事業期成会.
玉城村立船越小学校創立50周年事業期成会編1997『創立50周年記念誌』.
宮里政玄1966『アメリカの沖縄統治』岩波書店.
屋良朝苗1969『沖縄はだまっていられない』エール出版社.