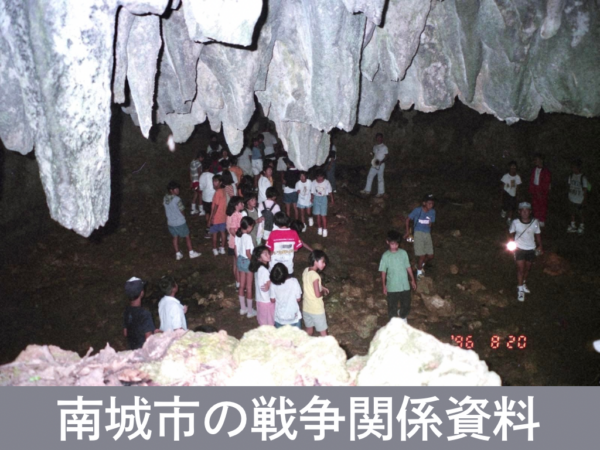
南城市の戦争関係資料リンク集

④知念グループ「徳広さんから見た沖縄戦」

2024年度沖縄国際大学経済学部経済学科 専門演習IB(小濱ゼミ)南城市の戦後産業調査

今回、私たちは南城市の産業の歴史について調査するにあたって、南城市玉城親慶原のファミリー向けレストラン、「チャーリーレストラン」に関心を持ちました。「チャーリーレストラン」は2024年9月30日をもってレストラン営業を終了し、現在はパイの持ち帰り専門店として営業しています。オーナーの山入端宏光さんにお願いして、50年以上の長きにわたって人びとの胃袋を満たしてきた「チャーリーレストラン」の創業から現在にかけての歴史を伺いました。
現在も南城市親慶原には、「チャーリーレストラン」のほかにも多くのレストランやカフェ、居酒屋などが立地しています。近くには、2024年の8月にできたばかりの「コストコ」や、1977年開業の「琉球ゴルフ倶楽部」などの大きな施設もあります。親慶原には重要な文化財もあり、1つ目はお宮と呼ばれる拝所(うがんじゅ)です。この拝所は戦後6代目の区長であった徳元八一氏の提案によって建てられました。かつては米兵がやってきて、ここで礼拝を行う姿もあったのだそうです。2つ目は大川(ウッカー) と呼ばれる井泉です。もともと集落における主要な水源のひとつとして、生活用品や洗濯場として使用されていたのだそうです。


また、親慶原では、区民運動会やエイサーなどの地域行事も活発に取り組まれています。これらの地域行事には、県外からの帰省者もしばしば参加しているそうです。さらに、青年会のOB達が年に2回ほどお年寄りの屋敷の清掃を行っているそうで、地元を愛する若者が多いといった印象を受けました。
戦後、親慶原には、「琉球列島米国軍政府」(第二次大戦後、米国軍が沖縄に設置した統治機関)がおかれました(1946年)。 近くの新里の高台に「沖縄民政府」が移転したこともあって、親慶原には多くの政府関係職員や労働者が住み始め、簡易裁判所や銀行、警察署なども設置され、発展していきました。また戦後、基地建設のころ接待の際に利用される料亭が3つ4つあったようです。1949年に大型の台風が沖縄を襲った際に、高台にあった沖縄民政府の建物は大きな被害を受けました。これをきっかけに、民政府や軍政府などの関係機関は那覇へと移転していきました。しかし、広大な米軍施設は親慶原に残されたままでした。この施設は地元の人々の働く場となり、多くの人が軍での仕事に従事することになりました。この施設は海軍司令部として使用された後に、陸軍、CIAと変わっていきました。その後、基地として使われていたその敷地は沖縄が日本に復帰した2年後の1974年に返還され、跡地にはゴルフ場が建設されました。

宏光さんは、幼いころの親慶原について、比較的豊かで治安も良かったと言います。小学5年生のときにようやく電気がつくようになりましたが、それ以前も、行事などの際には米軍基地の部隊が発電機を提供して電気を供給してくれていたそうです。
そのようななかで、宏光さんの父である宏正さんは、1973年に「チャーリーレストラン」を創業しました。地域密着型のファミリーレストランを掲げ、1階にはテーブル席、2階には宴会会場がありました。宏正さんは南城市玉城にあったCIA(アメリカ中央情報局)の秘密施設「キャンプ知念」でコックを務めていました。その経験を活かして、沖縄が日本に復帰した翌年に、40代でレストランを開業しました。宏正さんの愛称がチャーリーだったことから、「チャーリーレストラン」という店名になったそうです。
宏光さんによれば、宏正さんが目指していたのは、「…とにかく地域に定着と言っていて、もう別にどっかからお金持ちを呼んで良いものをだそう、フランス料理出そうとか全くない。やっぱり敷居の低い店、誰でも気軽に入れるような店」でした。メニューは、基本的には宏正さんや宏正さんと同じく基地内で働いていたところから「チャーリーレストラン」に移ったコックたちで考えたもので、基地内で作っていたメニューを沖縄の人向けにアレンジして提供していました。酢豚もあるし、ステーキもある、沖縄そばもある、といったように、和洋中を揃えていました。こうしたスタイルは、本土では珍しいそうです。さらに、米軍の部隊があった頃には、当時は珍しかった英語併記のメニューを採用して外国人客にも対応しました。特にステーキメニューは地域で評判となり、近隣の飲食店でも取り入れる店が増えていきました。
「チャーリーレストラン」が創業したころの親慶原には、今でいうところの「居酒屋」はありませんでした。宏光さんは、当時の様子を、「夜、もう23時ごろまで飲み客がいっぱい。ジュークボックスを置いているからジュークボックスをかけながら、飲んだら帰らんのよ。」と思い起こしていました。米軍部隊関係の女性がよく踊っていて、それを見るためにおそらく志喜屋方面から飲みに来たであろう住民もいたそうです。5年ほど経ち、今でいうところの「割烹」が近くにできるまで、こうした状況は続きました。
「チャーリーレストラン」の特徴の一つは、当時は珍しい「ドライブイン」スタイルをとったことでした。
戦後から経済が発展するにつれて、沖縄でも車を持つ人びとが増えていきました。宏光さんが幼いころには、親慶原で車を所有する家庭は少なく、あったとしてもピックアップトラックのような仕事用の車がほとんどでした。乗用車を所有するのは、特別な必要性がある人、例えば集金など仕事上、どうしても必要な人くらいでした。そのため、ほとんどの住民は移動手段としてバスを利用していたといいます。車の台数は数えるほどであり、バスに乗れば十分事足りるというのが当時の人の感覚でした。
しかし、その後の時代の変化とともに、車を購入する際にローンが組めるようになりました。特に若い世代では車を持つことが一種のステータスとなり、ドライブが流行りました。当時、「チャーリーレストラン」の近くにあった新原(みーばる)ビーチには、たくさんの人が遊びにきていました。デートやレジャーなどのために車で移動する人びとを狙いました。
ドライブインの運営を始めるにあたっては、アメリカのハイウェイ沿いに見られる飲食店などで、小窓から商品を手渡しする形態や注文を受けて車内に料理を持っていくスタイルを念頭に置いていました。当時はマクドナルドのようなファストフードチェーン店がまだ普及していなかったため、ハンバーガーや軽食がドライブインの主力商品として注目を集めました。宏光さんは、次のように回想します。「新原(みーばる)にだんだん皆さん、車も乗ってバスでも来るし、そしたらその時にハンバーガーとかまだマックがなかったから、けっこうたくさん出たのよ。」
今回の聞き取りで「チャーリーレストラン」を訪れた際、レジの周りには、たくさんのサイン色紙や訪れたお客さんの感謝の手紙が飾られているのを見ることができました。このような手紙が送られていることで、どれだけこの店が愛されていたかを実感することができました。
私たちは、「チャーリーレストラン」を通して南城市の歴史について知らなかったことをたくさん学ぶことができました。50年以上もお店の経営をすることは簡単なことではなく、バブル期や消費税の導入、コロナ禍と様々な出来事が起こりました。バブル期のようにお客さんがたくさん来てお店が繁盛することもあれば、消費税や新型コロナウイルスによる営業の縮小を要請されることでお店の経営が難しくなることもありました。しかし、そんな中でも店主の宏光さんは「地域とのつながり」や「従業員を大切にすること」ということを大事にしていました。時代が変わることでその時代に合わせた新しい制度が設けられることや、コロナウイルスのような突然起こってしまうこともある中で、そのような想いだけは創業当初から変わっていなかったことが今回の調査で学ぶことができました。社会の変化に合わせて私たちも変わることは大切だと思います。しかし、変わらない想いを持ってレストランの経営をしてきたことが、「チャーリーレストラン」が50年以上も愛されている理由だと感じることができました。 最後になりましたが、本調査にあたり、インタビューを快くお引き受けいただいた「チャーリーレストラン」オーナーの山入端宏光様に厚く御礼申し上げます。