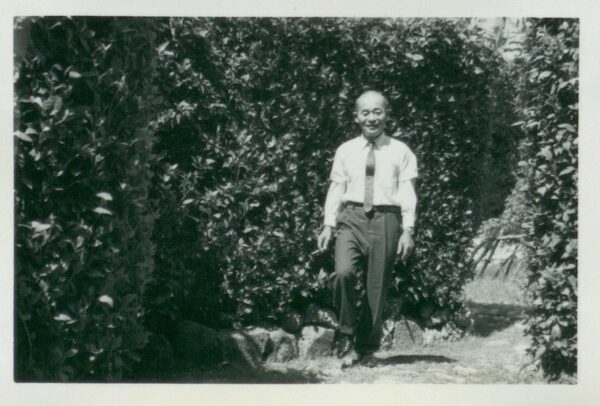
【資料群紹介】上原清光コレクション
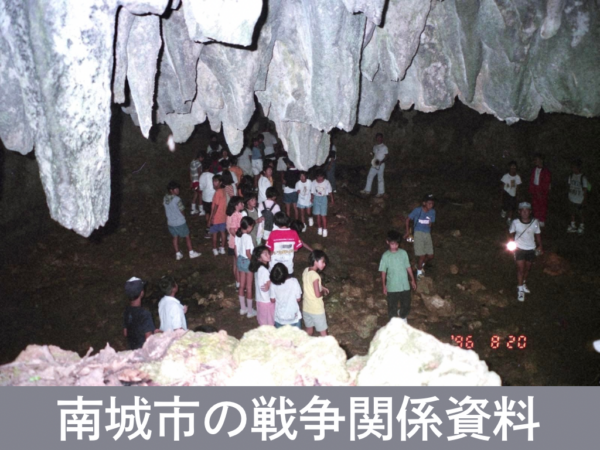
南城市の戦争関係資料リンク集

議会議員城間盛亀(団長)・普天間善徳・小谷森青・平田源善の4議員と議会書記徳本善成氏の5氏が、日本本土の行財政、産業視察研修のため日本本土へ東京向け出発する(10月21日迄)。10月4日には、名古屋で養豚業を視祭する。
【コラム】本土移住者の活躍
参考資料:広報さしき 第4号(1965年2月) PDF
城間団長をはじめとする一団は、10月4日、名古屋で、仲伊保出身の知念泰司氏の案内により、佐敷村出身者(富祖崎出身の玉寄兼蔵氏、屋比久出身の呉屋善英氏含む)の養豚業を視察しました。視察では次のことがわかりました。①かれら佐敷出身者はいずれも200頭乃至300頭を多頭飼育し養豚業で成功している。②飼料は残飯、芋、または購入飼料。③現在価格は生体で十斤4セント。
また、一団は10月9日、沖縄物産販売大阪斡旋所長と会い、「大阪の豚肉卸販売業者から豚の輸出を要求されているが沖縄からの出荷がない」という話を聞きました。しかし、当時は、島内消費でさえ不足している状況にありました。沖縄の豚輸出業者は、生産過剰になり、なおかつ、生体30セントから32セントに価格が落ちた場合には輸出も出来ると考えていました。
佐敷村議員玉城源光(副議長、団長)・普天間善徳・屋嘉部景興・瀬底正麗の4名、佐敷村役場固定資産評価員宮城福光は、本土の産業発展の実状を見るために視察研修を行う(11月11日迄)。
●10月24日、岐阜県大垣市島里町にある南農業協同組合を視察。同地では、農業多角経営が目指され、養豚、養鶏、酪農等で農家収入が向上していた。
●10月25日、愛知県安城市姫小川町芝山にある桜井農業協同組合を視察。同地でも、農業多角経営が行われていた(養豚、養鶏、肥育牛等、野菜作り)。
佐敷村養豚組合が結成される。
佐敷村農協(小波津厚一組合長)は、大宜味村農協とのタイアップにより、村内の子豚の出荷を開始する。
【コラム】佐敷村の養豚
参考資料:広報さしき 第20号(1969年1月) PDF
養豚において品種の改良と防疫、肉質改善は重要なテーマです。それらについて、佐敷村は、『広報さしき』第20号(1969年1月)で、養豚農家に向けて、次のように依頼していました。
「養豚をなされる際は常に品種の選定と防疫に気をつけて改良された良い素豚を飼い、健康に管理して損耗や、飼料の無駄を防ぎ併せて労力を効率的に活用して、よい肉を速く、安く生産して畜産収入の増大につとめて下さい」
「家畜の病気が発生した場合、畜主は家畜伝染病予防法により村長に報告する義務がありますので遅滞なく報告して下さい」
「本村の肥育牛はすべて雄牛が肥育されております、雄牛は18ヶ月以内に出荷できる時はよいとして、それ以上肥育する場合は肉質が低下して売上値も良くありませんので出来得るだけ去勢し、肉質改善につとめ高値で出荷できるように努力していただきたいと思います」
第2回沖縄県畜産共准会(県畜産共進会主催)において、「ヨハネス・ボストン・カツ譲」が経産豚の部で優等賞を受賞する(佐敷村初)。
【コラム】養豚一筋 吉田勇さん
参考資料:広報さしき 第41号(1976年6月) PDF
「ヨハネス・ボストン・カツ譲」を飼育したのは吉田勇さん。吉田さんは、戦後まもない混乱期に、村の振興には養豚が一番と考えて、いち早く養豚に取り組みました。それ以来、養豚一筋。畜産共進会などで常に優秀な成績を納める吉田さんは、母豚6頭、雄豚2頭、育成豚7頭、仔豚25頭を飼育するまで事業を拡大するようになりました(1976年当時)。
吉田さんは、1973年12月に、佐敷村養豚組合を結成し、結成と同時に副会長に就任しました。佐敷村・農協とタイアップして、技術の向上、優良品種の導入、経営の合理化などを行い、一貫として養豚振興のために取りくんできました。
なお、吉田さんは、1976年5月から、大宜味村農協と佐敷村農協の提携による仔豚の共同出荷にも関わるなど、流通面の開拓にも積極的に取り組みました。
佐敷村農協が大宜味村農協とタイアップして始めた子豚の出荷数が1,800頭となる(1976年度実績)。
【コラム】大宜味村農業協同組合と佐敷村農業協同組合との協働でスタートした養豚事業
出典:広報さしき 第46号(1977年1月) PDF
佐敷村農業協同組合(以下、佐敷村農協)は大宜味村農業協同組合(以下、大宜味村農協)と協働で養豚事業を始めました。
佐敷村の基幹産業は、サトウキビ栽培でした。そのような状況のなか、佐敷村農協は次のビジネスモデルで養豚事業を行なっていました。
① 佐敷村農協が肉豚を産むための母豚を飼育する。
② 佐敷村農協が養豚農家へ母豚を売る。
③ 佐敷村農協から母豚を購入した養豚農家は母豚に種付をする。
④ 養豚農家の母豚が肉豚を出産する。
⑤ 養豚農家が農業協同組合の経由により肉豚を出荷する。
このようなシステムに加え、さらに佐敷村農協は三者協議会(佐敷村農協と大宜味村農協と農家代表)を開いてしました。同協議会は1ヶ月に1回の頻度で行われていました。佐敷村農協や大宜味村農協のほか、養豚農家らは同協議会により、肉豚の販売ルートを確立させていました。肉豚の販売ルートを確立することは肉豚の取引価格が下落しないように価格調整をすることにつながります。
このような努力の甲斐もあり、佐敷村内の養豚事業の現状は1976年には次のようになっていました。
・年間出荷頭数 1,800頭(当初の出荷目標を300頭も上回る)
・年間売上金額 2,800万円
さらに、佐敷村内の養豚事業は進展を遂げた結果、1977年には次のようになっていました。
・養豚農家の数 53戸
・母豚の数 250頭
・肉豚(子豚)の平均取引価格 1頭あたり1万1,000円程度
・出荷1回あたりの売り上げ 60~70万円
・母豚1頭から1年間に18頭以上の肉豚が生産される
・50頭以上の肉豚が毎週水曜日に出荷される
これらの好況について佐敷村農協の小波津厚一組合長は「2年前から始めた子豚の出荷も順調に伸びており、今後は販売路を拡大し、これからも養豚農家を育成していきたい」と述べています。
第9回沖縄県畜産共進会が開催される(7日迄)。佐敷町にかかわる豚の成績は次のとおり。
【種豚(経産2類)】
金賞一席 新里やす子(兼久)
●佐敷町出身者が同会において初めて金賞を受賞した。
【コラム】佐敷町で初の金賞一席を受賞した新里やすこさん
参考資料:広報さしき 第73号(1983年2月) PDF
新里さんは、受賞する数年前までは、会社勤めをしていました。はじめは、姑さんがやっていた養豚にさほど興味を示さなかったといいます。ところが、姑さんが寄る年波に勝てず豚を手放すことを検討するようになった時、新里さんはふと「私にもできないかしら」と思うようになりました。そして、家族と相談し、彼女にまかされることになりました。残パンの収集、えさの準備、掃除など、悪戦苦闘の毎日を過ごすようになりました。
沖縄一になるまでに、残パンを快く提供してくれた人、家族(とくに姑さん)、同業者の援助など多くの人々にささえられたといいます。
彼女は母豚を養っていました。「子供が一度にたくさん生まれるでしょう。その中からこの子はじょうぶな母親になりそうだと見わけるのがむつかしい。それがまた楽しみなんですね」と語っていました。